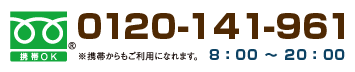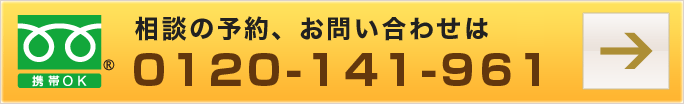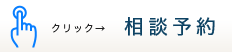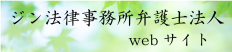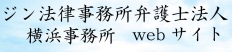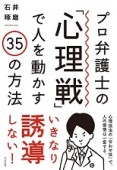よくある質問
FAQ(よくある質問)
寄与分は民法改正でどう変わりましたか?
寄与分と民法改正(2019年7月1日施行)についての話です。
寄与分は相続の際に、相続人が被相続人の財産を増やしたり、減らさずに維持したことについて、通常の寄与以上に、特別の寄与、貢献をしているようなケースで、その貢献分を評価して取り分を増やす制度です。
ただ、特別の寄与が認められるハードルは結構高くて、通常の介護では認められにくいです。
この寄与分については、相続人に認められるものなので、例えば父母、子2人のような家族関係で、長男の妻が親を介護しても、相続人でないため、相続のときに寄与分としては考慮されないという点が問題視されていました。
長男の妻問題です。
長男の代わりとして介護した、などの理論構成はあるのですが、すべてのケースで救済できるわけでもなく、問題とされていました。
民法改正で、親族も寄与分の請求が可能に
今回の改正で、この寄与分について、相続人でなくても、親族であれば、請求できることとなりました。
特別な寄与を無償でしたときには、親族は、寄与分部分の請求ができ、相続人間で話がつかなければ、家庭裁判所に金額を求めることができるようになりました。
この寄与分については期限が決められています。相続があることや相続人を知ってから6ヶ月、相続開始から1年という期限がありますので、ご注意ください。
特別寄与者の課税
この特別寄与制度では、課税関係に注意が必要です。
この特別寄与者によって請求される特別寄与料は、相続人以外の親族が相続人(特別寄与料の支払義務者)に対して請求するものです。
特別寄与者が被相続人から相続又は遺贈により取得する財産ではありません。
しかし、相続人と特別寄与者との間の協議や家庭裁判所の審判で決められることや、期間制限があること、遺産額を限度とすることなどから、被相続人の死亡と密接な関係がある性質のものです。
そこで、相続の中で課税すべきとされました。
この際には、被相続人が相続人以外の人に対し遺贈した場合と比較する必要があります。
このような流れで、特別寄与料に対しては、相続税を課税することとされました。
被相続人から特別寄与者に対する遺贈とみなすこととされたものです。
特別寄与料の相続税の計算方法
特別寄与は、遺贈とみなすとされたので、相続税の計算は、遺贈と同じになります。
相続人以外の人が遺贈で財産を取得した場合の計算です。
基礎控除のうち1人当たり600万円の控除はありません。
特別寄与料で相続税の総額を按分、特別寄与者の算出税額を求めることになります。
相続人でもないので、2割加算となります。
葬儀費用の控除
特別寄与者が、被相続人の葬式費用を負担していると、特別寄与料から葬儀費用を控除した金額を特別寄与料として扱うものとされています。
相続人でもないので葬儀費用を負担することは多くないかもしれませんが、負担している場合には控除計算を忘れないようにしましょう。
3年以内の贈与の課税価格への加算
相続開始前3年以内に、被相続人からの贈与がある場合、贈与された財産の価額が相続税の課税価格に加算されます。
直近の贈与を相続税で処理するという流れです。
特別寄与者の相続税の申告期限
特別寄与料の請求が認められた寄与者も申告が必要です。
特別寄与料の支払額が確定したことを知った日の翌日から10か月以内とされます。
相続人側の相続税
特別寄与料の支払額が、相続税の課税価格に算入される場合、その支払をする相続人の相続税の課税価格は、取得した財産から、特別寄与料の負担額を控除できます。
支払いが発生しているので、その分を課税から差し引く扱いです。
複数の相続人がいる場合には、特別寄与料の額を法定相続分で割り振った金額を負担するものとされるので、これを課税価格から控除することになるでしょう。
特別寄与料の支払いによる相続税の更正の請求
特別寄与料の支払義務者になる相続人が、相続税の申告期限までに申告を済ませた後、特別寄与料の問題が出てきて、自らの負担に属する特別寄与料の支払額が確定したという流れの場合、特別寄与料の支払額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求ができるものとされています。
特別寄与料が短期間で決まらない場合には、このような対応になることが多いと思われます。