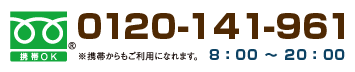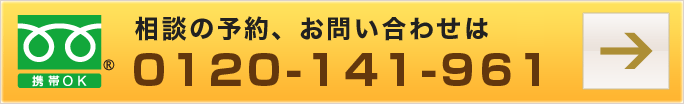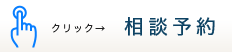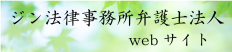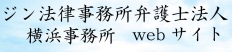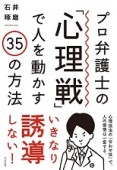よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.親族の特別寄与料の程度、期限は?
親族による特別寄与料の請求が認められるのか問題になった裁判例があります。
法改正でできたばかりの制度ですので、認められるかどうか少ない裁判例をチェックして検討する必要があります。
静岡家庭裁判所令和3年7月26日審判を解説します。
今回の事例では、
療用看護が特別の寄与になるのか
また、6ヶ月の期限を過ぎているのではないか
が問題にされています。
特別寄与料請求の事案の概要
被相続人は、令和2年3月に死亡し、相続が開始。
申立人は弟。
相手方は、前夫(離婚)との間の子2人。長男と二男。
離婚の頃から被相続人とは疎遠。
申立人と相手方らは、離婚の頃までは叔父と甥としての交流があった関係。
申立人は、相手方らの氏名は知っていた、一人の住居は知っていたという事情です。
相手方らが、被相続人の相続人(子)、申立人は弟という立場で寄与料の請求をしたという事案です。
特別寄与料の条文
親族による特別寄与料の条文は、民法1050条です。
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
相続開始と特別寄与料請求までの流れ
被相続人は、令和2年3月19日に死亡。
申立人は、同日、被相続人死亡の事実を知り、同月20日までには、二男の住居を訪れ、その住居の郵便受けに、被相続人が死亡した事実や葬儀の日程等を記載した手紙を入れ、被相続人の葬儀を執り行いました。
葬式会場を訪れた二男と再会。
そこで、遺産相続の話をしました。
申立人は、遺産である預貯金の解約等の手続を進めます。
相手方らは、申立人に対し、同年8月頃、手続に必要な書類として、委任状や印鑑登録証明書、戸籍謄本を交付。
申立人は、被相続人の遺産の3分の1を取得したいと相手方らに伝えたところ、同年10月に相手方らが弁護士をつけこれを拒絶。
そこで、申立人は、令和3年1月20日、静岡家庭裁判所に本件調停の申立て。
同年5月14日、調停不成立となり審判手続に移行。
特別の寄与があるといえるかどうか、また、期間が争われました。
死亡から6ヶ月以内である8月頃に相続関係の書類のやりとりがあり、6ヶ月経過後に弁護士からの拒絶通知を受け、その後に調停申立という流れになっています。
特別の寄与になるか?
特別寄与になるような療用看護があったかどうか問題になります。
家庭裁判所は、被相続人が通院や入退院をするようになった平成8年「6月から申立人の妹が体調を崩した平成27年6月までの間は、被相続人の身元引受人として主に被相続人に関与していたのは妹であって申立人ではなく、その間の申立人自身による関与は年に数回程度面会等に訪れるといった限定的なものにすぎない」と指摘。
同月以降についての関与も、仮に申立人の主張を前提としたとしても、月に数回程度入院先等を訪れて診察や入退院等に立ち会ったり、手続に必要な書類を作成したり、身元引受けをしたりといった程度にとどまり、専従的な療養看護等を行ったものではない、これをもっても、申立人が、その者の貢献に報いて特別寄与料を認めるのが相当なほどに顕著な貢献をしたとまではいえないとしました。
また、申立人は、死亡後に葬儀等の手続をしたことも民法1050条1項にいう特別の寄与として主張したものの、特別の寄与として考慮し得るのは相続開始時までのものに限られるから、被相続人死亡後にした寄与に係る主張は主張自体失当として否定しています。
その結果、その者の貢献に報いて特別寄与料を認めるのが相当なほどに顕著な貢献をしたとまではいえないとして、特別の寄与を否定しました。
このような事実では、特別寄与とまでは認められないという判断がされています。
特別寄与料の除斥期間も経過
家庭裁判所は、民法1050条2項ただし書は、除斥期間を規定したものとしました。
その起算点について、相続の開始を知った時のみでなく「相続人を知った時」にもかからしめたのは、特別寄与者が家庭裁判所に対する特別寄与料に関する処分の請求に及ぶことを期待し得ない場合にまで除斥期間が経過してしまうことのないようにするためであるとしています。
その例として、相続人の存在等を覚知できなかった場合や、特別寄与料の支払を請求していた相続人が特別寄与者の知らないうちに相続放棄をしていたような場合を挙げています。
そこから、「相続人を知った時」とは、当該相続人に対する特別寄与料の処分の請求が可能な程度に相続人を知った時を意味するものと解するのが相当であるとしました。
今回の事例では、被相続人が死亡する前から、二男の氏名及び住所について認識しており、実際にその住居を訪れてもいたと認定。
被相続人が死亡した令和2年3月の時点で申立人が「相続人を知った」と認められるとしました。
また、長男についても、申立人が、同年8月16日頃、長男より任意に委任状や印鑑登録証明書等といった重要書類を
託されていることに鑑みれば、遅くとも、預貯金の解約等の手続に関する連絡を取れるようになっていたと考えられる同年5月頃の時点では長男につき申立人がその住所地を二男から聞き取るなどして調査することは容易であったと考えられるとし、同時期に「相続人を知った」と認められる」としています。
これにより、本件申立ては、除斥期間を経過した後にされたものと結論付けています。6ヶ月が過ぎていたので、NGという判断です。
このロジックですと、認識していなくても調査容易であれば、相続人を知ったと判断されるということになります。
特別の寄与料制度とは?
法改正前は寄与分と呼ばれていた制度の論点です。
寄与分では原則として相続人しか請求できませんが、長男の妻、などの近い親族が介護を行っていた場合に、長男の寄与分とみなして請求できないか問題になっていました。
この点を新しく制度として導入したのが、親族による特別寄与料の請求です。
特別寄与料は、相続人ではない親族が被相続人の療養看護に努めるなど貢献した場合、その貢献に応じた金銭の請求ができる制度です。これを特別寄与料と呼びます。
本来、相続人でない人が、相続財産の一部を受け取れる制度です。
特別の寄与とは?
特別の寄与は、貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献が必要とされます。
通常の寄与分の請求では、被相続人との身分関係から通常期待されるような程度を超える貢献が必要とされます。たとえば、子ならこの程度の介護は通常のものであるとされ、寄与分が否定されるという裁判例も多数あります。
これに対し、今回の特別の寄与料では、身分関係によって程度を変えるようなものではないと言われます。
ただ、できて間もない制度であることから、寄与料の判断では、相続人の寄与分での判断基準が参考にはされるでしょう。
療養看護による寄与分では、療養看護の必要性のほか特別な貢献が考慮されています。
近親者による療養看護が必要であったのかどうか、被相続人の要介護度、入院、施設入所などが判断要素とされそうです。
これらの証明のため医療記録や介護記録等を提出する必要も出てくるでしょう。
今回は、それなりの付き添いや身元引受人になるなど、かなりの貢献をしているように見えますが、特別の寄与が否定されています。
特別寄与料の期限
特別寄与料に関する調停・審判の申立ては、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内及び相続開始の時から1年以内にしなければならないとされています(民法1050条2項)。
6か月の期間は、請求の相手方になる相続人ごとに個別に計算されます。
相続人のうち1人は期限が過ぎたものの、1人には間に合った、という事態もありうるわけです。
この権利行使期間の性質は、除斥期間とされています。
家庭裁判所は、起算点となる「相続人を知った時」について、「当該相続人に対する特別寄与料の処分の請求が可能な程度に相続人を知った時を意味するものと解するのが相当」としました。
そして、その判断の際には、事実認識以外に、調査可能性という要素まで使われています。
法定相続人ではないものの、その財産維持等に貢献したという人は、特別寄与料の請求をするのであれば早めに動くようにしましょう。
今回の流れだけを見ると、分配に協力するように見せておきながら、6ヶ月経過後に弁護士をつけて法的に主張して拒絶されると、特別寄与料の請求を断念させることができるように見えてしまいます。あまりにもひどい場合には、信義則などで主張が否定されることはありえますが、従前の寄与分請求と同様に、特別寄与料の請求も認められるハードルが高いという印象です。
寄与料、相続のご相談をご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。