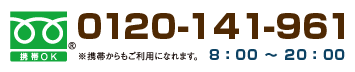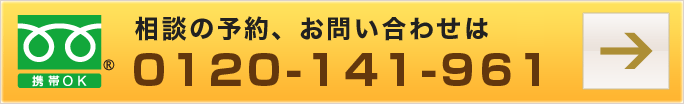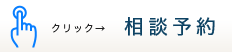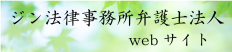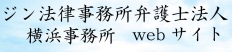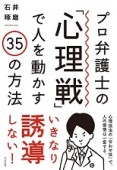よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.遺言無効確認訴訟のポイントは?
遺言無効確認訴訟で勝訴できるかどうかは、複数の事情によって変わります。
また、地裁と高裁で異なる判断がされることもあります。それだけ、判断にばらつきがある分野です。
今回も、判断が分かれた事例から、どのような事情がポイントになるのか取り上げてみます。
東京高等裁判所令和元年10月16日判決です。
遺言無効の事案の概要
被相続人は母。
自筆証書遺言の有効性が争われた事件です。
被相続人の子らが、兄弟姉妹間で争ったという内容でした。
原告が、遺言書の成立の真正は認められないと争うとともに、遺言書記載の作成日において遺言者の遺言能力が失われていたと主張。
遺言無効確認訴訟を起こしました。
地方裁判所は遺言有効
一審である地方裁判所は、遺言を有効だとしました。
遺言書の成立の真正は肯定。
遺言書の作成日時点において、認知能力に相当な低下があったものの、自ら料理や買物を行っていたもので、日常生活は自立しており、本件遺言書作成日の約3か月後においても、預金の払戻手続に必要な書類の作成を自ら行う程度の能力は有していたことが認められることなどから、遺言能力はあったと判断しました。
高等裁判所は遺言無効
高等裁判所は、遺言書の成立の真正については肯定。
ただ、遺言能力については、否定。原判決を取り消して、請求を認容。
遺言無効と判断したものでした。
どのような事情により、遺言無効と判断されたのでしょうか。
遺言無効となった事情
本件遺言書が作成されたのは平成21年12月4日。
当時、日常生活はある程度自立していたものの、
火の消し忘れが目立つようになっていた、
妄想や物忘れがしばしば生じていた、
子が銀行や郵便局からお金を取ってきたという妄想も短期間のうちに繰り返していた、
郵便局において、平成22年当初ころまでに、認知症によって被相続人が要領を得た会話ができなくなり、一人では貯金の払戻しも困難な状態となっていた、
そのため、単独で郵便局に訪れた場合には貯金の払戻しをさせず、子の誰かが同伴している場合に限って貯金の払戻しを可能とする取扱いを始めていた、
平成22年1月19日に被相続人を診察した医師は、認知症の疑いで紹介状を作成、
同年2月9日に被相続人を診察し医師らは、いずれもアルツハイマー型認知症との診断をした、
という事実がありました。
さらに、遺言書の作成方法は、子が被相続人に提案し、その内容も口授したものを、被相続人が自書したものでした。
このような事情から、高等裁判所は、遺言書作成時点において、認知症によって、自己の財産状況を把握し、その処分について決定することができなくなっていたと認めるのが相当と結論づけました。
成年後見の診断内容
そして、この認定判断は、平成22年2月17日以降、被相続人の精神科での主治医が作成した、成年後見開始申立用の診断書、鑑定書等の内容ともよく整合するものとしました。
同時期の長谷川式スケールは17点。
同年3月24日にはアルツハイマー型認知症であると診断。
特段の事情のない限り、認知能力は徐々に低減していくものであることを踏まえ、本件遺言作成の前後の事実経過からすると、本件遺言の内容が単純であることを考慮しても、本件遺言書の作成時点において、被相続人は、遺言の内容及
びその法律効果を理解した上で遺言をする能力を欠くに至っていたというべきであると結論付けました。
地方裁判所と高等裁判所で判断が分かれる形となった事案です。
遺言能力の判断要素
遺言者に遺言能力がなければ、遺言は無効となります。
遺言能力があるかどうかをどう判断するのかというと、裁判例では、諸要素を考慮して総合的に判断しています。
つまり、判断にバラツキがありうるものです。
その中でも、遺言者に精神上の障害があるかどうか、その内容や程度、
遺言内容の複雑さ
遺言をする動機があるか、遺言で利益を得る人との人間関係
遺言に至る経緯
あたりはよく取り上げられます。
今回の事件では、遺言当時の明確な診断はないものの、その後の診断がある。
そこからの推認が必要。遺言当時にもいくつかの怪しいエピソードがあるという点がポイントになりました。
判断が分かれるような微妙な事案だったということがわかります。
同様の事例は、多数あると思われ、遺言無効を争いたい人は、訴訟提起してみる価値がある内容といえるでしょう。
遺言無効確認訴訟のご相談をご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。