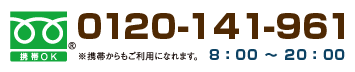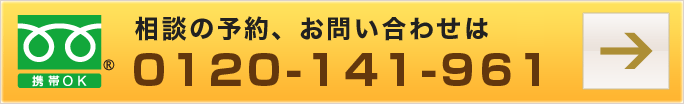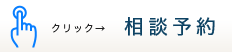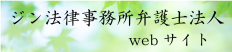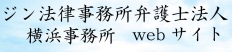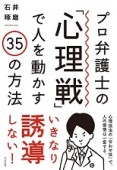よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.遺言に書く年月日は遺言完成日?
自筆証書遺言に書かれた年月日が、実際の遺言完成日とは違うとして、遺言無効を争われた事例があります。
高等裁判所までと最高裁で異なる判断がされています。
結論としては、原則として、遺言完成日の記載をしないといけないが、違うからといって、直ちには無効にならないという判断がされています。
最高裁判所第1小法廷令和3年1月18日判決です。
遺言無効の事案の概要
遺言者は、入院中でした。
平成27年4月13日、同日付け自筆証書による遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書で作成。
その後、退院。退院から9日後の5月10日に、遺言書に押印。この際、弁護士が立会っています。
遺言者は5月13日に死亡。
遺言者には、戸籍上の妻がいましたが、別に内縁の妻もいるという状態。
遺言内容は、内縁の妻に相続財産が渡るものでした。
そこで、法定相続人である戸籍上の妻らが、この遺言は無効だと裁判を起こしたというものです。
その内容として、本件遺言書に本件遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているなどと主張したのでした。
本文を書いた日を年月日として記載して、違う日に押印をした点が問題になったものです。
高等裁判所までの判断
法律上、遺言作成年月日は必須の記載事項とされています。
高等裁判所は、このような前提から、本件遺言は、遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているという方式違反により無効としました。
本件遺言書には押印がされた平成27年5月10日の日付を記載すべきであったというものでした。
一応、自筆証書である遺言書に記載された日付が真実遺言が成立した日の日付と相違しても、その記載された日付が誤記であること及び真実遺言が成立した日が上記遺言書の記載その他から容易に判明する場合には、上記の日付の誤りは遺言を無効とするものではないと解されるが、本件では、そのような事情がなく無効という結論でした。
妻の請求を認めた内容でした。
最高裁判所の結論
それだけで無効にはならないとの判断でした。
原判決を破棄して、高等裁判所に差し戻し。
遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではない、他の事情を審理すべきとして、差し戻したという内容です。
遺言成立日は完成日
自筆証書によって遺言をするには、真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならないと解されるところ、本件遺言が成立した日は、押印がされて本件遺言が完成した平成27年5月10日というべきであり、本件遺言書には、同日の日付を記載しなければならなかったにもかかわらず、これと相違する日付が記載されていることになると前提確認。
しかしながら、民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にあるところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがあると指摘。
したがって、遺言者が、入院中の平成27年4月13日に本件遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年5月10日に押印したなどの本件の事実関係の下では、本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきであるとしました。
以上によれば、本件遺言を無効とした原審の前記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとしました。
この点に関する論旨は理由があり、原判決中本訴請求に関する部分は破棄を免れず、本件遺言のその余の無効事由について更に審理を尽くさせるために、これを原審に差し戻すのが相当としました。
簡単に、形式的な違反だけで判断するのでは、不十分であるとの結論です。
遺言書の形式的要件
自筆証書遺言が有効であるためには、形式的な要件を満たす必要があります。
法律で決められている形式的な要件としては、その本文、日付及び氏名を自書すること、これに印を押すこととされています。
日付の記載が必要なのは、遺言能力があるかどうかの判断基準時や、複数の遺言書が発見された場合に、どちらが先に作られた遺言かを判断するためです。自筆証書遺言は、証人も立会人もいないことが前提ですので、作成された日は、遺言書に書かれている日から判断するしかないことが多いのです。
複数の遺言書が見つかり、内容が矛盾する場合には、新しい方の遺言内容が優先されます。
そこで、遺言書に書く日付は、真実遺言が成立した日と解釈されています。
本件のように、遺言作成が、何日にも渡った場合には、完成した日を遺言成立日とするとされています。
遺言作成日間違えでも有効になる事例
遺言作成日が実際の遺言作成日と違っても、必ずしもすべての遺言が無効になるわけではありません。
勘違いなどの場合には、有効になるとされています。
判例では、「誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、右日付の誤りは遺言を無効ならしめるものではない。」とされています。
遺言の方式を厳しくしすぎると、遺言者の意思に反してしまいます。
本件では、日付が違うだけでは無効にならないと判断しています。
遺言書に押印した際には弁護士が立ち会っていることから、遺言成立日の認定自体は、疑われにくいという前提もあったと思われます。
というか、弁護士が立ち会っていたのであれば、そこで日付を修正させれば良かったようにも感じます。体調面などで、そこまでの余力がなかったのでしょうか。
遺言作成が複数の日にまたがる場合に、いつの日を記載するのかについて、判例とは違い、先行した日を記載するという考えもないわけではないので、その考えを採用したのかもしれません。
ただ、そこで修正しなかったことから、このような遺言無効確認訴訟まで起こされている、すきを作ってしまったといえるでしょう。
遺言には完成日を書く
遺言の完成日を書くようにしましょう。
本判決では、日付が違っても、遺言が「直ちに」無効とはならないとしているに過ぎません。
無効になる可能性もまだまだあります。差し戻して審理されることになっています。
これから遺言を作る人は、このような紛争にならないようにするためにも、遺言を完成させた日を記載するようにしましょう。
自筆証書遺言を完成させるのに、何日もかかる人は、日付はとりあえず保留、完成した日に記載するようにしておきましょう。
遺言書、相続のご相談をご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。