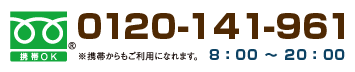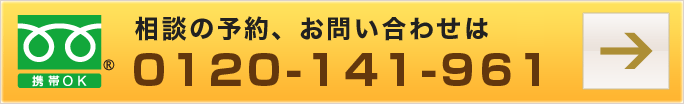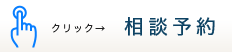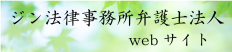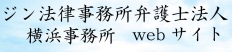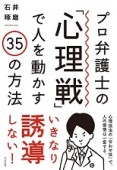よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.代理母で特別養子縁組は認められる?
海外の代理母制度を利用して特別養子縁組が認められるのか問題になった裁判例があります。
裁判例は少ないですが、特別養子縁組は認められています。
静岡家庭裁判所浜松支部令和2年1月14日審判でも、これが肯定されています。
海外での代理母制度で母親は代理母になる
日本の法律、裁判例では、海外で代理母を依頼した子の母親について、依頼した夫婦の嫡出子としたり、懐胎出産していない依頼母を母とすることは難しいとされています。実の親子とすることは認められていないわけです。そのため、日本国内では、代理母が出生した子の母とされます。
そこで、依頼した母と子との間の親子関係を認めてもらうために、特別養子縁組制度が使われることになります。
今回の事件では、申立人らは、いずれも現在25歳以上の夫婦。
申立人らの間に実子はなし。現在、いずれも健康で、十分な世帯収入があると認定されています。
代理母利用の経緯と認知
申立人らは、申立人母が罹患した疾患の治療の結果、懐胎、出産ができない状況にあることから、海外での代理母出産のあっせんを業とする企業に、海外での代理母出産を依頼。
ウクライナ国において、ウクライナ国籍の養子となる者の母(代理母)が申立人ら間の体外受精でできた胚の移植を受け、懐胎し、平成31年、未成年者を出産。
申立人父は、未成年者の出生に先立つ平成30年、未成年者を胎児認知。
申立人らは、平成31年、未成年者を引き取り、申立人母が、同年月末頃までウクライナ国に滞在し、未成年者を監護養育。
その頃、申立人母と未成年者はウクライナを出国し、日本に入国。
以後、申立人らは、申立人ら肩書住所地において、未成年者を監護養育しているという経緯です。
ウクライナでの代理母手続き
ウクライナ法上、生殖補助技術を適用したことにより夫婦間で受精した胚を、他の女性の体内に移植する場合、当該夫婦が子の両親であるとされ、代理母は、平成31年、ウクライナ国の公証人の面前で、未成年者は、生殖補助技術を用いた代理出産として出生したものであり、未成年者の出生届に遺伝学上の父母である申立人らが父母として記載されることに同意する旨を宣言していました。
申立人父と代理母は、平成31年、協議により、未成年者の親権者を申立人父と指定。同日、未成年者につき、国籍留保の届出がされています。
特別養子縁組の申立てと調査官調査
申立人らは、令和元年6月10日、本件特別養子縁組手続きを申し立てました。
その後、家庭裁判所調査官による申立人ら宅での面接を含む調査がされました。
その結果、未成年者は、申立人らの監護養育の下で、概ね順調に成長し、医師の経過観察が必要な点も、申立人らにおいて適切な受診等の対応がなされていること、未成年者と申立人らとの間で親子としての愛着関係を築かれていることが確認されました。
申立人らの監護意欲、監護能力、監護環境や未成年者と申立人らとの適合性に問題は見当たらないと報告されています。
適用されるのは日本法であることの確認
審判では、日本法が適用されることが確認されています。
養子となる者の母である代理母はウクライナ国籍であるが、養親となるべき者である申立人らはいずれも日本国籍であり、養子となるべき者である未成年者は、ウクライナ国籍および日本国籍を有するが、日本を常居所としているため、法の適用に関する通則法38条1項により日本法が本国法となり、同法31条1項により、特別養子縁組の成立については、日本法が適用されることが確認されています。
家庭裁判所は特別養子縁組を認める
申立人らの養親としての適格性、申立人らと未成年者との適合性に問題はない一方で、代理母は、そもそも未成年者が申立人らを実親とし、申立人らに監護養育されることを予定して未成年者を懐胎しており、代理母が未成年者を監護することは著しく困難で、未成年者を申立人らの特別養子とすることが、その利益のために特に必要があるといえると指摘。
また、代理母は、申立人らの子として未成年者の出生が届け出られることに同意しており、その同意は、代理母と未成年者との間の日本法上の母子関係を終了する効果を有する日本法上の特別養子縁組への同意を含むと解され、父母の同意その他の特別養子縁組の成立要件にも欠くところはないと認められるとしました。
これにより、特別養子縁組を認めています。
代理母と特別養子適格についての意見
代理母の制度については、意見が分かれています。
代理懐胎自体に否定的な意見も多いです。
そのようななかで、代理母制度により出生した子との特別養子縁組を認めると、この代理母制度を助長してしまうのではないかという意見もあります。このような意見だと、特別養子縁組は認められないという結論になりそうです。
しかし、そもそも代理母は、子を自身の子として育てる意思を持っていないのが通常です。特別養子縁組を否定すると、生まれた子の行き場がなくなってしまいます。
そこで、特別養子縁組については、代理母制度を利用した経緯、動機等を考慮して、判断すべきではないかと言われています。
特別養子縁組の要件である実母の同意
特別養子縁組が成立するためには、父母の同意(民法817条の6)が必要とされています。
日本では、代理母が出生した子の母とされています。
そこで、特別養子縁組の要件とされる父母の同意には、代理母の同意が必要になります。
特別養子縁組では、通常の養子縁組よりも、実の親子間の関係が極めて弱まります。そのため、実親の同意が要件とされたり、手続上も、実親の陳述を聴取しなければならないとされているのです。
しかし、海外での代理母制度では、もともとが、生まれた子と依頼者の親子関係に同意しているはずです。しかも、出生直後から子は依頼者に引き渡されています。代理母が子を養育するようなことは想定されていません。代理母は特別養子縁組にも同意するのが通常でしょう。
そこで、実親の陳述についても、書面など簡易な方法でされるべきではないかと提案されています。
今回の審判でも、出生届の同意が特別養子縁組の同意を含むものとし、緩やかに認定されているといえます。
特別養子縁組等のご相談をご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。