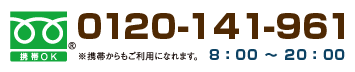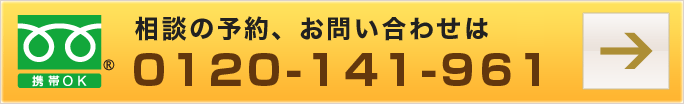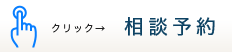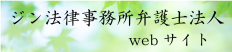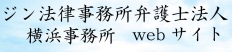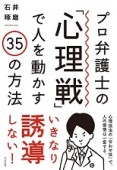よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.自筆証書遺言の保管制度とは
2020年から始まった自筆証書遺言の保管制度について解説します。
遺言書作成で悩んでいる人は、チェックしてみてください。
自筆証書遺言の保管制度とは
遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度です。
よく使われる遺言には、公証役場で作る公正証書遺言と自分で書く自筆証書遺言があります。
遺言書保管制度ができたことにより、自筆証書遺言のデメリットがかなり減っています。
遺言書保管制度は、令和2年7月10日から始まっています。
法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づく制度です。
自筆証書遺言のメリット、デメリット
自筆証書遺言は、どこでも作成できる、費用もかからないというメリットがあります。
これに対し、公正証書遺言のように管理がされているわけでもないので、デメリットもあります。
たとえば、遺言者の死亡後に、遺言書が発見されない、紛失してしまうなどが想定されます。
また、公証役場の公証人の立ち会いもないため、遺言書の偽造、改ざん等を主張され、遺言無効確認の裁判を起こされることもあります。
さらに、自筆証書遺言では、形式上のルールが厳しく決められているため、ルール違反による無効というリスクもあります。
加えて、自筆証書遺言で、不動産の登記を移転させるには、家庭裁判所の検認手続が必要とされており、これが面倒だとも言われます。
遺言保管制度のメリット
遺言保管制度は、このような自筆証書遺言のデメリットを減らす制度です。
法務局で、自筆証書遺言を預かる制度です。その際、明らかな形式違反があれば、指摘されます。
一応の確認がされるという点で、単純な形式違反で無効とされるリスクを減らせます。
また、発見されない、紛失してしまう、改ざんされてしまうというリスクも大幅に減ります。
遺言書保管制度はどのくらい利用されているか
遺言保管制度は、法務局で行われています。
この手続を利用するには、 事前予約が必要とされているので、ネットから予約してから行くことになります。
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
公表されている統計データからは、2021年3月末時点までの利用件数として、遺言書の保管の申請件数の総数は、約16700件とされています。
遺言書保管制度の手続
遺言書について、保管制度を利用したい場合、保管の申請をします。
この申請のために、予約をしてから法務局に行きます。自分で行く必要があります。
保管の申請手数料は、申請1件につき、3900円です。
保管の年数や、遺言書の枚数によっても変わりません。
申請手続が完了すると、氏名、生年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が書かれた保管証が交付されます。
死後、この保管証が相続人に発見されれば、遺言保管制度を利用していることが分かるというわけです。
遺言保管制度による保管期間
保管される遺言書は、遺言書の原本及び遺言書の画像データとして保管されます。
保管期間については、遺言書の原本は遺言者の死亡日から50年間、画像データを含む情報は、死亡日から150年間とされています。
画像データは複数の拠点で保管されます。
そのため、何らかの災害等で遺言書原本が滅失しても、画像データは保管されている可能性が高いです。
遺言書保管後に閲覧できる
遺言書の保管が開始された後、遺言者は、預けている遺言書の原本を閲覧できます。
書いた内容を忘れてしまうなど、内容を確認したければ、法務局に行くことで分かるという制度です。
控えやデータを持っておけば、閲覧までする必要性は高くないですが、いざというときには安心できる制度です。
ただ、遺言書の原本の閲覧は、保管申請を行った遺言書保管所だけでの対応です。
手数料は1回につき、1700円とされています。
遺言書原本ではなく、遺言書の画像データを観るだけの場合、全国の遺言書保管所で対応してくれます。こちらは、1回につき1400円。こちらの方が利用ニーズは高そうです。
個人情報の関係で、遺言者の生前に閲覧できるのは、遺言者のみです。
親族などでも生前に閲覧はできません。
閲覧の際には、本人確認のための資料の提示が必要とされます。
遺言書保管後の住所等の変更
遺言書を預けた後に、氏名・住所等が変更されることもあります。
遺言内容は変えなくても、このような形式的な内容に変更がある場合です。
このような場合、届け出が必要になります。
遺言者本人、受遺者又は遺言執行者の氏名、住所等に変更が生じたときは、遺言書保管官にその旨を届け出なければな
らないとされています。
手数料はかかりません。
自分自身の氏名、住所等の変更の場合には、住民票の写しや戸籍謄本等の提出が必要になります。
遺言書保管の撤回
一度、遺言書を保管申請しても、やっぱり止めたいと撤回することもできます。
保管の申請を撤回すれば、遺言書の返還等を受けることができます。
手数料はかかりません。
遺言者本人のみができます。
遺言自体の取消とは違いますので、預けた遺言書をやっぱり手元に置いておきたいというようなケースに使う手続きです。
遺言書の保管申請をしても、その後に新しい遺言書を作ること自体はできます。
相続人による手続き
相続人が遺言保管制度に関われるのは、遺言者の死後となります。
遺言者の死亡後により相続開始後、相続人や受遺者、遺言執行者等は、遺言書が保管されているかどうか等を証明する遺言書保管事実証明書の交付請求ができます。
遺言書保管事実証明書の手数料は、1通800円。
郵送請求もできるとされていますが、請求人自身の住所への送付とされます。
遺言書が保管されていない場合や、請求人の関係遺言書ではない場合には、関係遺言書が保管されていない旨の遺言書保管事実証明書が交付されることになります。
遺言書情報証明書の交付
保管されている遺言書があるとわかったら、関係相続人等は、保管されている関係遺言書について、内容を証明する遺言書情報証明書の交付の請求ができます。
こちらの手数料は、1通1400円。
これにより、どのような遺言書だったのか遺言書の内容を確認できます。
この交付の請求では、遺言者の全ての相続人を確認できる書類を添付する必要があります。
法定相続情報一覧図の写しを利用することもできます。こちらの方がラクでしょう。
遺言書保管制度からの相続人への通知
遺言書保管所の遺言書保管官が、関係相続人等に対し、遺言書情報証明書を交付した際には、その他の関係相続人等に対して遺言書を保管している旨が通知されます。
他の相続人に対しても、遺言があるという存在を明らかにする通知となります。
自筆証書遺言の検認手続でも、他の相続人への連絡がされます。これと似たように、全相続人が遺言の存在を知ることになります。
なお、遺言者からあらかじめ申出があった場合、遺言者が死亡した際に、関係相続人等のうち1名に通知がされる制度もあります。
自筆証書遺言の財産目録
自筆証書遺言は、以前は、全文が自筆でなければならないとされていました。
この点について法改正がされています。財産目録などはパソコンで作成したものは通帳などの資料のコピーを添付することでも良いとされました。
財産の一覧を打ち込んでおき、自筆する本文で特定すれば良いことになったものです。
ただ、財産目録のページには署名・押印をする必要がありますので、注意が必要です。
保管のための自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言では、法律で決められている形式的なルールがあります。
保管制度を利用する場合には、それ以外にもルールが決められています。
これは省令で決められています。
例えば、用紙サイズ。
A4サイズと指定されています。さらに、ページの記載、余白設定などが必要です。
保管制度を利用しないのであれば、このようなルールは無関係です。
保管制度では、画像保存などもあるため、形式的なルールが別に作られているので、注意してください。
自筆証書遺言の保管制度を利用する場合でも、遺言書の作成自体は自分でする必要があります。
法務局で遺言書作成自体ができるわけではありません。
ジン法律事務所弁護士法人では、元となる自筆証書遺言書の作成などのご相談にも対応しております。
遺言のご相談をご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。