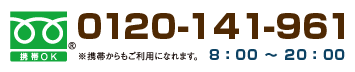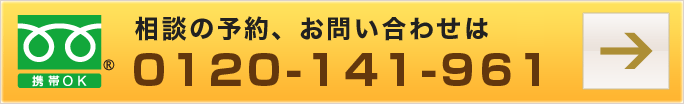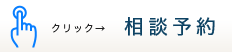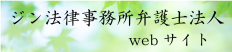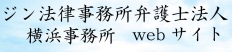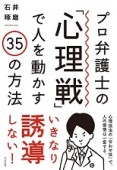よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.遺言が無効とされる場合とは?
相続紛争を避けようとして遺言書を作ったにも関わらず、遺言無効、有効を争う紛争が起きてしまうこともあります。
遺言が無効になってしまう場合とはどのような場合でしょうか。
遺言を作成する人
最近は、若い人でも遺言を作成ことが増えてはいますが、遺言を作成する人の大部分は高齢者と言われます。
夏休みの宿題を先送りしてしまうように、死が近づき、意識する年齢にならないと、行動に移せないのですね。
また、ある程度の資産がある年齢にならないと、遺言を作っておくかという気持ちにならない人も多いです。大した遺産もないから、遺言なんて作らなくても大丈夫だろうという考えです。
このように、遺言を作成する人の多くが、高齢である場合、有効性をより意識しないといけません。
加齢とともに、遺言が無効とされてしまうリスクが高まるからです。
遺言が無効とされるケース
では、遺言が無効とされてしまうケースは、どのようなものなのでしょうか。
まず、前提として、遺言を無効だと主張する人がいるのです。
たいていは、遺言内容によって不利益を受ける相続人です。
法定相続分より取得分が少ないなど、不公平感を抱く相続人が争うことがほとんどです。
そのような遺言内容で、遺言作成状況に問題があると、無効だと争われる、判断されることが出てくるわけです。
たとえば、遺言者が認知症で、遺言を作成できるような状態ではない、遺言者の判断能力の減退に乗じて、同居家族などが自分に有利な内容の遺言を作成させていると疑われるケース、遺言内容の不自然な書き換えがあるようなケース、などで遺言能力がないとして遺言が無効だと主張されることもあります。
遺言能力とは
法律上、遺言者には遺言能力が必要です。これがないと無効になります。
民法963条では「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」とされています。
この解釈が問題になるのです。
遺言能力がないとして有効性を争われる事件では、遺言者が認知症など能力低下の状態にあり、これが遺言能力と結びつくのかが曖昧なのです。
遺言能力について、裁判例では、遺言時の遺言者の病状、精神状態等のほか、遺言の内容や遺言経緯等の要素から判断されています。
医師の意見が確認されることもありますが、最終的には裁判官の判断で決められます。
医師が認知症と診断していただけでは、無効になるものではありません。
たとえば、民法では、認知症患者も多い成年被後見人でも、遺言をすることを前提としています。
973条では、事理弁識能力を一時的に回復した場合は、医師2人以上の立会いによって遺言を作成することが認められています。
認知症の症状の進行は、認知症の種類や、人によって違います。
病状や精神状態
認知症に限らず、病状や精神状態も遺言能力の有無の際に考慮されます。
そのため、遺言者が通院しているような場合には、病院から診療記録(カルテ)の取り寄せによって、症状の確認がされることになるのが通常です。
また、介護を受けているような場合には、介護事業者から介護日誌などのサービス提供記録や担当者の聞き取りがされることもありますし、市町村で介護認定の際の調査票が開示されることもあります。
遺言無効を主張する場合には、可能な限りこれらの資料を集めたうえで、検討することになります。
遺言内容
遺言能力の有無を検討する際には、遺言内容も重視されます。
これらは関係があります。
遺言内容が複雑な場合には、それなりの判断能力が求められますし、単純な内容であれば、比較的低い能力でも遺言能力があると判断されやすくなります。
遺言能力は、かんたんに決まるものではなく、遺言内容との関係で判断されることになります。
遺言に至る経緯
最近の裁判例では、遺言に至る経緯も細かく認定されたり、証人尋問でも追及されたりしています。これは動機に関係するものと思われます。
そのような遺言を作成する動機が遺言者にあったかどうかを探っています。
遺言者の生活状況等から、裁判所が遺言内容が自然だと考えれば、有効に働きやすいですし、不自然に映れば無効に働きやすくなる要素です。
遺言内容が変更されているような場合、生活状況が変わったので、新しく親密になった親族の取り分を多くした、というような場合には、有効になりやすい経緯となります。
遺言者の言動から、同居家族に支配されていると感じるような事件では、周囲の影響力が強く自由に意思決定できたか
否かを慎重に判断している事例もあります。
自筆証書遺言と遺言無効
公正証書遺言よりも自筆証書遺言のほうが無効と争われやすいです。
公正証書遺言では、公証人が聴取するほか、証人も同席しているので、それだけ本人の意思確認がされており、無効にはなりにくいとされます。
これに対し、自筆証書遺言では立ち会い人も不要のため、作成時の状況を証言する人はいない点が無効になりやすい要素です。
また、自筆証書遺言だと、専門家が入らないケースも多く、形式面で無効とされることもあります。
自筆証書遺言においては、本文、日付及び氏名を自書し、押印をしなければならないとされています。
このあたりのミスで無効にされた例も多数あります。
遺言作成の際には、無効にならないよう遺言能力の証明、形式面のチェックなど専門家に相談しながら進めるようにしてください。
遺言・相続を含む高齢者の家族問題等のご相談は以下のボタンよりお申し込みください。