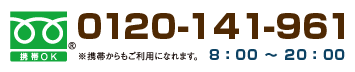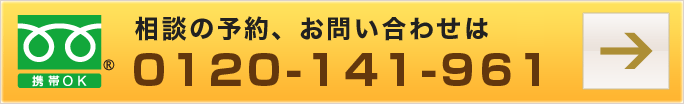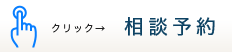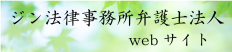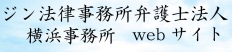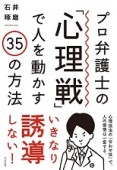よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.高齢者の医療保険、介護保険の内容は?
成年後見、任意後見事件や介護がからむ扶養事件などでは、医療保険や介護保険に関する相談も多くありますので、これらの公的保険の概略を解説しておきます。
高齢者の保険
高齢者に関わる家族間の紛争が増えています。
また、高齢者の犯罪が起きてしまった後の社会復帰のシーンなども含めて、日本の保険制度の仕組みを押さえておく必要があります。
金銭面での問題が原因になることも多いため、各種保険制度をフォローしておくことで、これらの問題を減らせることになるでしょう。
日本の医療保険制度、介護保険制度では、皆保険制度が採用されています。
つまり、全ての国民が加入することになっています。
全国民が、保険料を払うことで、誰で保険による給付を受けられるという仕組みです。
もちろん、保険料の支払ができないなど、支払能力も考慮され、保険料の金額や給付の範囲は、所得などによっても変わってきます。
高齢者世帯の実情
統計上、65歳以上の高齢者がいる世帯については、夫婦だけの世帯が約750万世帯、単独の世帯が約660万世帯、親と未婚の子のみの世帯が約500万世帯とされています。
夫婦だけの世帯は、いずれ単独世帯になる可能性が高いですね。
ここから、これからの日本で、介護問題が大きな問題であることがわかります。
なお、高齢者世帯の所得金額の中央値は年間244万円とのことです。
所得から介護費用を捻出するとなると、かなり大変な数字になっています。
日本では、2022年には75歳以上人口が2000万人を超える見込みです。
さらに、介護の問題と切り離せない認知症についても数字が出ています。
2018年の認知症患者数は500万人以上。
文献によっては、65歳以上の高齢者の7人に1人が認知症とも言われています。
85歳~89歳では5割程度、95歳以上では9割以上の人は、要介護認定を受けています。
この年齢帯での、認知症の罹患率も高いと見込まれています。
今後、介護問題と認知症の問題が大きく日本の負担となっていくことが見込まれます。
医療保険、限度額認定の仕組み
私達が何気なく使っている医療保険は、相互扶助の仕組みが採用されています。
自分や家族に、不測の傷病が発生した場合に備えて、みんなが資金を保険者に捻出し、実際の保険事故が発生し、資金の必要性が生じた時に負担を和らげる仕組みです。
医療保険制度を使えるのは、国の指定を受けた医療機関です。
日本では、一部の美容整形外科等を除けば、ほとんどの医療機関がこの指定を受けており、意識せずに医療保険が利用できます。
医療保険に加入し、保険料を払うことで医療保険証を受け取り、使うことができます。
実際には、必要な医療を一部負担するだけで受けられるという仕組みです。
75歳以上の高齢者の場合は、後期高齢者医療制度の対象となります。
医療保険制度を使って医療を受けた場合、病院などの医療機関の窓口で払う金額は、治療費の一部なわけです。
その程度は、所得等に応じて1割から3割までの範囲です。
さらに、支払う金額が高額となった場合には、高額療養費制度もあります。これは、同一月で一定の金額を超えた場合、申請することで超過分が後日払い戻される制度です。
この高額療養費制度だと、一時的には支払いを立て替える必要があります。その資金が大変な場合、医療費が一定の金額以上になることが分かっているような場合には、あらかじめ市町村などの保険者に申請して限度額適用認定証をもらいます。これを医療機関に提示すれば、実際の医療機関への支払を自己負担限度額までに抑えることができます。
限度額認定証制度は、長期入院中の成年後見事件などで使うことも多い制度です。
なお、治療の必要性がないのに個室を選択した場合の費用や、入院に関しおむつ代など日常生活に要する費用については、医療費に関する自己負担限度額には含まれません。
認知症の増加
認知症患者は増加傾向にありますが、今後、さらに増える見込みです。
認知症は、日常生活に支障が生ずるほどに認知機能が低下してしまいます。
治癒することはない脳の病気といわれます。その進行程度は、認知症の種類によって異なります。
成年後見の診断で使われることの多い長谷川式スケールを開発した長谷川氏も、緩やかな進行度の認知症になり、自身の症状について書籍を出しています。
朝と夕方では、認知能力に差があることや、低下した場合であっても、周囲の考えなどはわかることを教えてくれています。
認知症を完全に避けることは難しく、認知症予防と呼ばれる場合も、認知症にならないというものではなく、認知症の発症を遅らせる、進行を緩やかにするという意味で使われることが多いです。
介護保険の仕組み
医療保険と同じく、相互扶助の仕組みにより、介護保険制度もあります。
介護問題とは切り離せない知識となります。
実際の利用の際には、居住地の地方自治体の施策、サービス提供事業者の状況等について、地域包括支援センター、ケアマネジャーに確認することになります。
介護保険により、65歳以上の人は介護保険被保険者証を受け取ります。
実際に、公的介護サービスを受けるためには、この保険証を持って市町村やケアマネジャー、医師等と相談し、要介護認定を受けます。
そして、必要な介護サービスの内容を選択し、ケアプランに落とし込みます。
このような流れなので、実際に介護サービスを受けるまでには時間がかかります。
介護サービス
介護保険制度による公的介護サービスを提供する主体は、都道府県などから指定を受けた社会福祉法人、株式会社、NPO法人等です。
その介護サービスには、訪問介護、通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)などがあり、これらのサービスを組み合せたサービルもあります。
公的介護サービスを受けたときに支払う金額は、介護サービス費の一部(所得によって1割~3割)で済むのです。
要介護認定の区分に応じて設定された金額があり、これを上限としてサービスが提供されることになります。
同一月で、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分は、後日、申請することで払い戻されます。
こちらも、医療保険と同じような話です。
介護保険法等の改正
令和2年6月に介護保険法等の改正法が成立しています。
改正法では、市町村による包括的な支援体制を構築するよう推進されています。
地方自治体による柔軟な事業が進められるよう制度設計されたものです。
高齢者世帯や、ご家族に高齢者がいる方は、行政の有益な情報をチェックしておいたほうが良いでしょう。
遺言・相続を含む高齢者の家族問題等のご相談は以下のボタンよりお申し込みください。