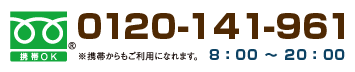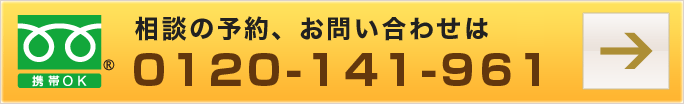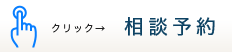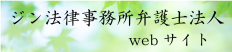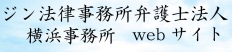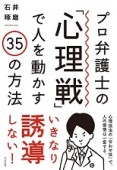よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.遺言が無効になってしまう書き方とは?
遺言が無効だと争う事件も多いです。
遺言無効確認訴訟を起こしたりします。
無効となる理由は色々ありますが、今回は、字の書き方が問題で無効とされた事例を紹介します。
字が読めなくて遺言が無効に
字が汚いという理由で自筆証書遺言が無効になってしまった裁判例です。
東京地裁平成26年10月29日判決です。
遺言では、死後に自分のの財産をどうするか一定の範囲でコントロールできます。
公証役場で作る公正証書遺言、自分で書く自筆証書遺言の2つがよく使われる遺言です。
動画での解説はこちら。
自筆証書遺言は法改正がされています。
昔は全文を自筆でなければならなかったのですが、今は、財産の目録は、パソコンや資料添付で良くなっています。
不動産がたくさんあったり、預金口座がたくさんあるような場合には、その特定部分については自筆でなくても良くなっています。
ただ、本文に関しては、自筆でなければなりません。
自筆証書遺言の形式ルール
自筆証書遺言には、形式上のルールがあり、これに違反すると遺言自体が無効になってしまうこともあります。
その形式名として
署名が必要
押印が必要
年月日の記載
などがあります。
作成年月日ですね。
通常、この3つは、遺言本文を書いたあとに、署名捺印、年月日をまとめて書くことが多いです。
年月日の記載が必要な趣旨は?
この年月日をどうして書かなければならないとかというと、遺言がいつ作成されたのか問題になることがあるからです。
まず、遺言能力があるのかないのかの参考にされます。
子供の頃に作っていたら、そもそも遺言能力が法的にないという話になります。
また、認知症だったりする場合には、その作成日にどのような症状が出ていたのか、通院記録がある場合には、それとの整合性が問題にされたりもします。
さらに、複数の遺言があり、内容が矛盾する場合、どちらがあとに作られたものなのか、法的に問題になります。
この年月日の記載がないと、このようなときに困るのです。
そこで、形式的に要件を満たしていないものとして無効になってしまうのです。
今回の裁判例でも問題になったのは、この年月日の点でした。
年月日が読めないから、記載がないものとして遺言が無効と判断されたのです。
年月日が読めない
今回の遺言では、まず、自筆証書遺言で縦書き。
最後の年月日欄を見ると、平成23年とは書かれていました。
その下には、なんか読めない字、その後、11月4日と書かれていたという内容です。
自筆証書遺言で、法務局の保管制度を利用していない場合、家庭裁判所での検認手続きをとります。
相続人の皆さんの前で開ける、中を見せる手続きです。
ここで、遺言をみて、「これはおかしい」と争う相続人がいると、遺言無効確認訴訟を起こしてくることがあります。
この場合、まず、遺言無効確認訴訟の結果を待ってから、相続手続きを進めることになります。
遺言の有効性を争う人がいるかどうかがポイントになります。
一般的には、遺言によって不利な扱いをされている相続人が争いやすいです。
今回は、年月日の「月日」の問題で、遺言無効確認訴訟となったわけです。
読めない字が、月にも見えるし、日にも見えるし、ただ上に何かついてるしと問題になりました。
読めない字の下には、はっきりと11月4日と書かれています。
その字との比較で、「一」という字にも「月」という字とも認定しにくいとしています。
文字の、はねや払いからして、あきらかに違う字であるとしています。
判決の中では、この遺言の年月日としては、読めない字が、十月の可能性、十一日の可能性に触れ、
読み方として、
十月十一月四日
十一日十一月四日
十一月十一月四日
不明十一月四日
と多義的に
11月4日、10月4日、11月11日とか読めてしまうとしました。
いずれの日であるか確定することができないとし、暦上の特定の日を表示するものとはいえず、日付の記載を欠くと判断しました。
文字が読めないことから、遺言全体が無効になってしまうという残念な結果です。
書き順が違うので遺言無効
もう一つ、遺言が無効となった裁判例を紹介します。
名前の書き順が違うということで、遺言が無効になったケースです。
札幌地裁平成30年2月28日判決。
動画での解説はこちら。
親が亡くなって、自筆証書遺言が発見。
家庭裁判所で検認手続きがありました。そこには、遺産を一人の娘に相続させるという文章がありました。
他の子が、この遺言はおかしいと主張。
遺言に記載されていた年月日は平成10年1月2日でした。
20年くらい前に書かれたという内容です。
ところが、この遺言が入っていた封筒は、その時期には販売されていなかったという不自然な点がありました。
他の相続人は、偽造だと主張し、遺言の筆跡鑑定を求めました。
実施された筆跡鑑定では、署名部分の書き順が問題になりました。
署名における自分の名字の後の名前。この一文字目の書き順が比較対象された文書と遺言書では違っていたのです。
全体の署名の比率なども違うものの、この書き順が違うという点は重視され、鑑定結果にも記されました。
裁判所の判決でも、この書き順を重視。
普通は、自分の名前の書き順を変えることないだろうということで、偽造によるものとして遺言は無効と判断しました。
封筒の発売日等で怪しいという印象を持った上での判断ではないかと思われます。
この判決から、遺言の際に、署名の書き順を普段と違うような書き方ですると、無効とされてしまうリスクもあるということがわかります。
お気をつけください。
遺言・相続のご相談は以下のボタンよりお申し込みください。