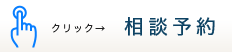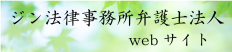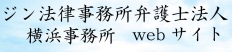よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.在日韓国人の預金相続は?
いわゆる在日韓国人の相続が争われたケースを紹介します。
準拠法は韓国法であるとされています。
大阪高等裁判所平成30年10月23日判決です。
事案の概要
在日韓国人である被相続人が、平成25年3月9日に死亡。
相続人は、配偶者、離婚した元配偶者との間の子がいました。
配偶者は、平成25年4月24日、銀行に対し、被相続人名義の普通預金、定期預金について、相続開始時の残高の法定相続分相当額の支払を求めました。
銀行がこれに応じないため、訴訟を提起。
一方で、銀行は、平成26年1月20日に、子に対しては、相続開始時の残高の法定相続分相当額を払い戻しました。
その後、銀行は、平成26年4月8日に、配偶者の法定相続分相当額を、債権者不確知を理由に弁済供託。
そして、本件訴訟に、子が独立当事者参加。
子は、配偶者に対し、各預金債権についての準拠法は日本法であること、準共有であることを主張、その各13分の3は被相続人の遺産であることの確認を求めました。
また、子は、銀行に対し、本件供託が無効であることを前提として、配偶者及び子が、本件預金債権の各13分の3の預
金者であることの確認も求めました。
今回の裁判では、預金債権の相続に関する準拠法が大韓民国法なのか日本法なのかが争われました。
原審は、原告の請求については、被告に約30万円の支払を求める限度で認容し、その余の請求を棄却し、参加人である子らの請求については、いずれも棄却。
参加人らが控訴し、一審被告が附帯控訴。
裁判所の判断
本件は、相続を原因として共同相続人らが普通預金債権及び定期預金債権を承継する場合にいかなる形態で承継しているかという問題であるから、相続による遺産の所有形態に関わるものとして、相続の効果に属するものとして性質決定するのが相当であって、相続の効果について規定した通則法36条により準拠法を決するべきとしました。
預金契約及びそれにより発生した預金債権の効力の問題ではないとしました。
ここから、本件預金契約という法律行為の成立及び効力と性質決定し、通則法7条及び8条により準拠法を決すべきではないとしています。
本件預金債権の相続については、韓国法が適用されて、韓国の大法院判例に従って、可分債権である本件預金債権は原告及び子らの法定相続分に応じて法律上当然に分割されて、本件預金債権の13分の3が原告に帰属するとしました。
判決では、例外的判断をする特別な事情があるとはいえないともしています。
通則法36条とは
通則法36条は、「相続は、被相続人の本国法による。」とする規定です。
被相続人の本国法によるルールは、相続統一主義と言われます。
本件では、被相続人の国籍は韓国でした。
そのため、韓国民法が適用されます。
これによると、法定相続分は配偶者が13分の3、子らは各13分の2でした。
韓国民法では、共同相続が発生した場合、被相続人の一切の権利義務は共同相続人に包括承継されるとともに、共同相続人は、法定相続分に応じて相続財産を共有します。
これにより、預金債権は、配偶者が13分の3、子らが各13分の2の法定相続分の割合で準共有となります。
そこで、預金債権が、当然分割なのか、遺産分割の対象になるのか問題となるのです。
韓国の遺産分割調停では、預貯金について、相続人から分割の対象にしないという申し出がなければ、そのまま遺産分割対象に含める例が多いようです。
特別な事情は?
判決でも触れられている、特別な事情についてですが、韓国では、共同相続人の中に超過特別受益者がいる場合や特別受益が存在し又は寄与分が認められ具体的相続分が法定相続分と異なりうる状況で、相続財産として可分債権のみがある場合のように、相続人の間の公平を図ろうとする民法第1008条、1008条の2の趣旨に反することになる特別な事情があるときは、相続財産分割を通じて共同相続人らの間で衡平を期する必要があるので、可分債権も例外的に相続財産分割の対象となりうるとしています。
当然分割を前提としつつ、例外的に相続財産分割の対象とするわけですね。
本件では、このような事情はないとして否定されています。
日本では、以前は、預貯金は当然分割とされ、相続人の合意により遺産分割の対象に含めるという扱いがされていましたが、現在は、判例変更により遺産分割の対象とされています。
死後の出金行為
本件では、被相続人の死後に預金からの出金行為があり、そのため、銀行はその点を調査し、支払いを拒絶するなどしていました。
しかし、本件普通預金債権の13分の3である642万4819円を一審原告が相続により取得していることは明らかであったと認められるから、被相続人の死亡の日以降に300万円の払戻しを受けたのが一審原告である可能性があったとしても、上記642万4819円から300万円を除いた部分については、一審原告に帰属することに変わりはないのであるから、一審被告が一審原告に払戻しをしないことを正当化する理由は見当たらないとしました。
そして、一審被告において、642万4819円全額を供託することはできないとしても、うち300万円については過失なく債権者を確知することができないとして民法494条後段により供託をした上で、300万円を除いた部分については一審原告に払戻しをするということが困難であったとも認められないとしました。
この点から、一審被告に遅延損害金の支払義務がない旨の一審被告の主張は採用できないと否定しました。
相続・遺産分割のご相談は以下のボタンよりお申し込みください。