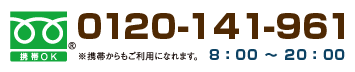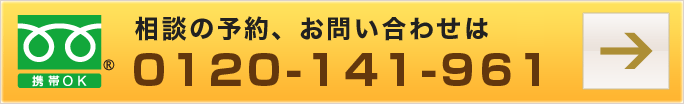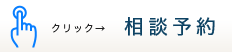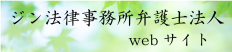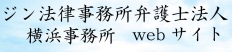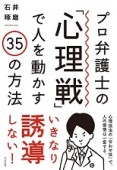よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.相続預金からの無断出金の扱いは?
遺産分割の中では、預貯金からの無断出金が関連問題として出てくることが多いです。
死亡前の出金
被相続人が亡くなる前に、相続人の一人が、被相続人名義の預貯金口座から出金することは、よくあります。
同居して親の面倒を見ている子が、親名義の預金口座の通帳、キャッシュカードを使って出金し、病院の費用支払、親の生活費支払をすることは多いでしょう。
親が高齢のため、自ら銀行に行けなくなっていることもあります。
親の承諾のもと、出金する行為は何ら違法ではありません。
これに対し、親の承諾もなく口座を管理し、権限がないのに無断で出金し、預金を流用する行為は違法です。
そのため、被相続人と同居していて、介護のほか、預貯金を管理していた相続人がした預貯金からの出金が、合法なのか違法なのか、被相続人の同意があったのか、その使途は、被相続人のためであったのかが争わることが多いです。
出金する際の権限や使途の明細記録があればよいのですが、このようなものがないと紛争が激化しやすいです。
取引明細の取得は?
無断出金が争われるような事案では、出金者が相続財産の預貯金の通帳や取引明細を開示しないということも多いです。
そのような場合、相続人としては、無断出金、使途不明金の調査のため、まずは金融機関から取引明細を取得する必要があります。
金融機関に対して請求する書類としては、預貯金口座の残高証明書のほか取引履歴があります。
残高証明書とは、決められた日の預貯金口座の残高を記した書類です。相続関係では、被相続人の死亡日、相続発生日のものと取得することが多いです。
取引履歴は、預貯金口座の入出金記録です。通帳と同じような内容が記載されています。
取引履歴をチェックすることで、過去の入出金を確認できます。ここで、不正な出金、不自然な入出金がないかを見ていくのです。
金融機関に対する残高証明書や取引履歴の開示請求は、相続人一人からでも原則として認められます(最高裁平成21年1月22日判決)。
「共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる」
なお、遺言等により、預貯金を相続しない相続人からは開示請求できるのかという問題はあります。2019年の時点では、そのような相続人からの請求も認められています。遺留分請求ができる立場という視点から認められているものです。
ただし、2019年相続法改正により、遺留分の法的構成が変わったことから、今後は開示請求できないのではないかという考え方もあります。
取引履歴の開示請求ができる期間
取引履歴の開示請求が認められるとしても、過去のすべての取引が開示されるわけではありません。
金融機関において、保管している期間に限られます。
この期間は、金融機関によって違います。過去10年間という金融機関もあれば、もっと遡れるところもあります。
開示手数料も金融機関によって違います。
出金伝票の開示請求
取引履歴をチェックし、不正出金が疑われる取引が、金融機関の窓口でされている場合、その出金を誰がしたか確認するため、振込依頼書や出金伝票の開示を請求します。
この開示義務については、解釈が分かれていて、開示請求に応じる金融機関と拒否する金融機関があります。
解約後の預貯金の取引履歴の開示請求は?
相続人が相続財産の預貯金を解約した後に、取引履歴の開示請求をすることもあります。
取引履歴の開示義務は、預金契約の契約者という立場から発生するもののため、この契約が解約された後は、いつまでも開示義務を負うものではありません。
法的には、開示請求は認められないのではないかという考えもあります。
実際には、ほとんどのの金融機関にで、解約後でも取引履歴開示に応じていますが、今後、どうなるのかは分かりません。
弁護士会照会による開示請求は?
金融機関が、任意に取引履歴等を開示しない場合に、弁護士会照会を使うことも考えられます。
弁護士会照会手続は、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するために、第三者に照会をする制度です。
弁護士会照会には、照会の必要性・相当性がないを除いて、回答する義務があるとされます。
法律上、相続人に開示請求する権利が認められる場合には、金融機関も回答してくることが多いです。
遺産分割調停における使途不明金問題は?
遺産分割調停で、当事者から使途不明金の問題が出されることはあります。
理論的には、相続開始前に被相続人に無断で出金された分は、被相続人から出金者に対して不法行為による損害賠償請求権や不当利得返還請求権という権利になります。この債権は、相続開始と同時に各相続人が分割取得します。
そのため、原則として遺産分割の対象とはなりません。
別途、訴訟等により、出金者に請求していく形となります。
無断出金と不法行為による損害賠償請求
無権限での出金行為は、違法行為となり、出金額を損害として不法行為による損害賠償請求をすることが考えられます。
ただ、出金額が正当な使途に支出されていたり、他の預金へ事実上振り替えられていただだけの場合、これは損害にならないとされるため、実際には、着服や被相続人の意思に反する使途への使用などがあったかどうかが問われることになります。
出金者の特定は?
預貯金口座から、誰が出金行為をしたのかについて争われることもあります。
銀行等の窓口での出金の場合、払戻請求書、出金伝票等の筆跡が有力な証拠になります。
ATMからの出金の場合、防犯カメラ映像が使えればよいのですが、現実的には、保存期間の関係や金融機関の協力の問題があり、これを証拠として使うのは難しいでしょう。
出金されたATMの場所が、どこであるのか、当時の被相続人が、そのATMまで行けたのか等から証明していくことになります。
出金額を被相続人に渡したという主張は?
無断出金の裁判の中では、出金した相続人が事実を認めつつ、使途について争い、被相続人に渡したという主張がされることも多いです。被相続人からの依頼で出金し、無断出金ではないという主張です。これが事実であれば、違法性はないと判断されます。
この場合、被相続人に渡したとされる額が、被相続人の生活状況からして不相当な金額であったり、それにもかかわらず使途を未確認だとすると、本当に渡したのか疑われることになるでしょう。
葬儀費用に使ったという主張は?
出金後、被相続人の葬儀費用に使ったから、不法行為は成立しないと主張することもあります。
葬儀費用を誰が負担するかという問題については争いがあります。
この問題点で、喪主負担ではなく、相続財産負担とする考えによれば、葬儀費用に使った分については、不法行為は成立しないことになります。
死亡後の出金
相続開始前ではなく、相続開始後、すなわち被相続人の死亡後に、相続人の一人が、預貯金から出金することもあります。
被相続人が死亡したにもかかわらず、その旨を金融機関に届け出なければ、キャッシュカード等を使って、預貯金の出金はできてしまいます。
このような出金があると、遺産分割時には預金として残っていない以上、遺産分割の対象に含めることはできないのが原則です。
改正相続法による対応は?
改正民法906条の2第1項では「遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。」とし、同条2項では「前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。」と定めています。
これにより、預金からの出金分について、出金者以外の相続人の同意があれば、これも遺産分割の対象として含めることができることとなっています。
なお、改正民法906条の2の規定は、遺産分割が行われる場合を前提としていますので、何らかの相続財産は残っていて、その財産について、遺産分割をする場合であることが必要です。
無断出金を伴う遺産分割のご相談は以下のボタンよりお申し込みください。