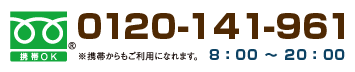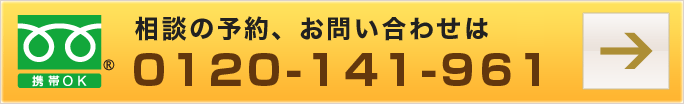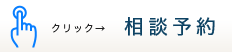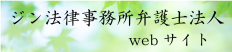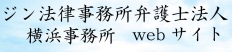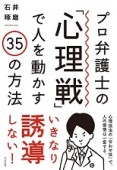よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.受遺者や受贈者への遺留分請求の順番は?
遺留分については、法改正がされています。
条文に修正があります。
受遺者、受贈者の遺留分
遺留分を持つ相続人は、受遺者や受贈者に対して遺留分請求ができます。
受遺者や受贈者の遺留分負担額について、改正民法1047条が規定しています。
1 受遣者と受贈者がいる場合、受遺者が先に負担します。
2 受遺者が何人もいる場合、受贈者が何人もいる場合で贈与が同時にされた場合、受遣者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担します。もらったものの価額で按分するのですね。
ただし、遺言で、別段の意思を表示したときは、その意思に従うことになります。
遺言者として、受遺者が複数いる場合などに、遺留分請求の負担順番を決めておくと、負担割合を変える事ができます。
3 受贈者が何人もいる場合は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担します。
死亡時に近い贈与から順番となります。昔の贈与ほど遺留分請求を受けにくくなります。
受遣者等が複数いる場合の負担の順序や割合については、民法改正前の1033条から1035条の定めが維持されたものといえます。
受遣者や受贈者の保護
改正民法1047条5項では「裁判所は、受遣者又は受贈者の請求により、第1項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる」と定めています。
特に、受贈者の場合、昔の贈与である可能性もあるため、「急に請求されても・・・」という事態を考慮して、裁判所に請求することで、支払を待ってもらえるという制度です。
遺留分請求のご相談は以下のボタンよりお申し込みください。