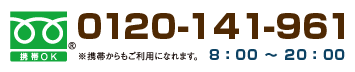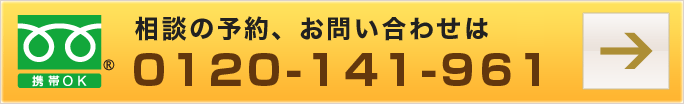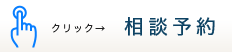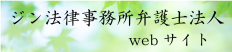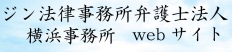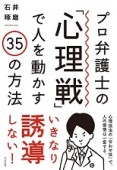よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.配偶者居住権とは?
配偶者居住権は、2020年4月1日施行予定の制度です。
自宅の所有権を配偶者が持たなくても、配偶者は自宅に住み続けることができる制度です。
2つの配偶者居住権
夫婦の場合、配偶者が死亡した場合に、今までに住んでいた家で住み続けたいと希望することが多いです。
特に、高齢者の場合、それまでの家を離れて生活環境を変えることは精神的・肉体的に大きな負担になることがあります。
このような経緯で、配偶者の居住権を保護しようとしたのがこの制度です。
改正民法では、
①配偶者が、被相続人所有の建物に、所有者が変わっても、終身又は一定期間という長期間、無償で住み続けることができる権利
②配偶者が、被相続人所有の建物に、その死亡から遺産分割で建物の所有者が確定するまでの短期間、無償で住み続けることができる権利
を認めました。
後者は一時的なものとして、配偶者短期居住権と呼ばれます。
配偶者居住権だとだけ呼ぶ場合には、前者を示すことが多いです。
この配偶者居住権は、被相続人が遺贈によって配偶者に取得させることができるものとされています。
この配偶者居住権は、相続財産の一部と構成されます。
遺産分割の中では、配偶者は、自分の具体的相続分から「配偶者居住権の財産評価額」を控除して、残額に相当する財産を取得することになります。
配偶者が配偶者居住権を取得した場合には、その財産的価値に相当する金額を相続したものと扱うとされているのです。
動画での解説はこちら。
配偶者居住権の成立要件
このような配偶者居住権が成立するには、、配偶者が相続開始時に建物の少なくとも一部に居住していたことが必要です。施設入居の場合に荷物もないような場合だと成立が難しくなります。
これは制度の趣旨から導かれた要件です。
共有物件については、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合でも配偶者居住権を取得できます。
夫婦共有というのはよくある話で、そこで、居住権が認められないのは不当です。
これに対し、被相続人が配偶者以外の者(他の共同相続人を含む。)と共有持分を有する建物については配偶者居住権は成立しません。
配偶者居住権の力は強く、共有者の権利を不当に害することになるからです。
また、配偶者居住権が発生した後に、居住建物が配偶者の財産に属することとなっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しません。
配偶者居住権を取得した配偶者が、居住建物の共有持分を取得しても、他の者が共有持分を有する場合には、配偶者居住権は消滅しないということです。
遺産分割の際、家庭裁判所は、次の場合に、配偶者居住権を取得させることができます。
1 共同相続人聞で、配偶者が配偶者居住権を取得することの合意
2 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申出、居住建物の所有者が受ける不利益の程度を考慮しても、なお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき
遺言と配偶者居住権
遺言で配偶者居住権を取得させる場合、「相続させる遺言」ではなく、遺贈でおこないます。
配偶者が配偶者居住権の取得を望まない場合、遺贈なら配偶者居住権のみ放棄することができます。
このような規定にも関わらず「相続させる」との遺言の場合には、それを遺贈の趣旨と解釈されることもあり得るでしょう。
配偶者居住権の範囲
配偶者居住権は、建物全体に成立します。
配偶者が相続開始時に、建物の一部に居住していれば、建物の全部に配偶者居住権が成立します。
例えば、建物の一部を間借入として賃貸していた場合、その賃貸借契約が終了した後、配偶者は、全体について配偶者居住権があることで、居住建物所有者の承諾がなくても、居住の用に供することができるとされています。
賃貸借契約終了までは、賃借人が引き渡しを受けているのであれば配偶者居住権に対抗できることになります。その賃料は、建物の所有者が賃貸人の地位を承継し、取得することになるでしょう。
もし、遺言で収益物件の賃料も配偶者に帰属させたいと考えるのであれば、その旨の記載が必要です。
自宅兼店舗の場合でも、建物全体に対して配偶者居住権の登記がされます。
配偶者居住権の存続期間
配偶者居住権により、どれくいらの長さで居住が認められるかという問題です。
法律では、配偶者居住権の存続期間を原則として終身としています。
死ぬまで住んでいられるという内容が原則という形式です。
期間の定めがあるときを例外的に規定している。
ただ、一般的には、期間の定めがされるのではないかと言われています。
期間の定めをせずに設定した場合でも無効にならないようにするため、終身規定を置いたとされています。
なお、登記の問題から、存続期間を「当分の間」「別途協議する」というような設定はできません。
配偶者居住権の財産的評価
配偶者居住権制度では、配偶者居住権を相続財産の一部と構成します
配偶者は、自分の相続分から「配偶者居住権の財産評価額」を控除した残額について相続することになります。
そうすると、配偶者居住権をどう評価するかという問題が出てきます。
明確な評価方法は決められていませんが、成立過程では、以下のような公式が意見として出されています。
例1:還元方式
(年額賃料相当額ー配偶者負担の必要費(固定資産税等))×年金原価率
配偶者居住権の経済的利益(賃料相当額等)に着目する方法です。
例2:簡易な評価方法
建物・敷地の価値-負担付所有権の価値
簡易な評価方法は、配偶者居住権の負担がない居住建物・敷地である土地又は敷地利用権の現在価額
から配偶者居住権の負担が付いた建物所有権と負担付の土地所有権又は敷地利用権の価額の合計額を差し引く方法です。
固定資産税評価額から算出できるとされます。
固定資産税評価額は、公示価格の70%程度とされています。そこで、70%で割り戻して時価を算出する方法があります。
この場合、負担付土地の価額は、敷地の固定資産税評価額÷0.7×ライプニッツ係数で算出されます。
配偶者居住権が存続している間は、敷地を使用収益できないため、配偶者居住権の存続期間満了までの期間分、割引き
をして現在の価値を求める方法です。
こちらは財産価値に注目する方法です。
収益価値と換価価値から大きく2種類の方向があります。これは借地権評価でも出てくる問題です。
配偶者居住権の相続税法上の評価方法
所得税法等の一部を改正する法律に伴い改正相続税法23条の2が平成31年4月1日から施行されています。
ここでは、配偶者居住権等の評価について以下の算出をします。
負担付き建物の評価方法としては、
建物時価から建物時価×((耐用年数ー経過年数ー存続年数)/(耐用年数ー経過年数))×存続年数に応じた法定利率による複利現価率の数値を差し引く
とされています。
また、負担付き敷地利用権の評価方法としては、
土地の時価から土地の時価×存続年数に応じた法定利率による複利現価率を差し引く
とされています。
配偶者居住権の価値は、これらを加算したものとされています。
小規模宅地等の特例利用の検討
配偶者居住権自体は建物の利用権に過ぎません。そのため、小規模宅地等の評価減特例は使えません。
しあkし、配偶者居住権者は、敷地利用権も取得しています。こちらの敷地利用権については、小規模宅地等の評価減特例に定める特例対象宅地等として適用があるとされます。
特例が適用されれば、敷地利用権の課税価格は、大きく減額されるので、これが使えるかどうかは検討すべきです。
配偶者居住権の節税効果は?
配偶者居住権は、配偶者死亡により消滅します。
一方で財産価値があるものとされます。
被相続人の死亡時に、配偶者に対して、終身の配偶者居住権を設定、不動産自体は子が相続すると、配偶者には、配偶者居住権の評価額について相続税が課税、子には不動産評価額から配偶者居住権の負担を控除した額について課税となります。
配偶者について、配偶者の税額軽減特例を使うと、法定相続分や1億6000万円までは相続税が課税されず、相続税負担なしで配偶者居住権を取得できることが多いです。
配偶者が死亡した場合には、子が相続した不動産では配偶者居住権は消滅することになります。
そのため、子の視点からすると、配偶者居住権を利用することで、この評価額分について節税ができるとされます。
ただし、死亡以外の配偶者居住権の消滅、すなわち合意や権利放棄などがあると、配偶者居住権評価額が贈与されたとみなされるため、贈与税の課税がされるリスクはあります。
相続税基本通達9-13の2で、死亡による消滅は贈与による取得とはみなされないとされていますが、今後、実務が変更される可能性もあります。
配偶者居住権の登記
配偶者居住権は、不動産に対する強い権利ですので、第三者へ公示させる必要もあり、登記できるものです。
建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の登記をする義務を負います。
登記される内容として、存続期間のほか、第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定めも登記されます。
配偶者居住権は、これを登記することで、居住建物について物権を取得した者などの第三者に対抗できます(改正民法605条の準用)。
賃借権の場合、占有が対抗要件となることもありますが、配偶者居住権は、登記のみが対抗要件とされています。
配偶者居住権の場合には、賃借権と異なり、建物所有者は、賃料収入すらもらえないものなので、第三者に配偶者居住権の存在をしっかり公示する必要性が高いことなどが理由とされます。
配偶者居住権の登記申請は、原則として、配偶者と居住建物の所有者の共同申請になります。
遺産分割審判等では、登記手続を併せて命じることになるでしょう。
「相続人Aは、配偶者Dに対し、本件建物につき、前項記載の配偶者居住権を設定する旨の登記手続をせよ。」
というような記載になるでしょう。
この場合は、裁判の判決等と同じく、配偶者の単独申請が認められます。
登記原因としては、遺産分割、遺贈、死因贈与に限定されています。
配偶者居住権と配偶者の義務
配偶者は、それまでの用法に従って、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならないとされています。
配偶者居住権は、第三者に譲渡してはならないとされています。
配偶者居住権の趣旨が、配偶者自身の居住環境を保護する点にあるため、第三者に配偶者居住権の譲渡を認めるのは、、制度趣旨と合わないことから、譲渡禁止とされました。
差し押さえもできません。
なお、居住建物の所有者は、配偶者居住権の制限付きの建物所有権を売却することはできます。
借地権、借家権等の負担付不動産を売却するのと似た関係になります。
配偶者は、建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができないとされています。
居住建物の使用及び収益に必要な修繕であれば、することができます。
所有者側としては、居住建物の修繕が必要なのに、配偶者が相当期間内に必要な修繕をしない場合には、修繕できるとされています。
配偶者には、居住建物が修繕を要するとき(配偶者が自ら修繕をする場合を除いて)には、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない義務があります。建物所有者が既にこれを知っているときは、この通知は不要です。
配偶者居住権と費用負担
居住建物の通常必要費は、配偶者の負担。
固定資産税や通常の修繕費は配偶者が負担することになります。
通常必要費以外の費用は、所有者負担。民法196条に従い、その償還をしなければならないとされます。
ただし、有益費の場合、建物所有者の請求により、裁判所は、その償還について相当の期限を許与することができます。
臨時の必要費(想定外の台風被害による修繕費等)や有益費(リフォーム費用等)については、建物所有者の負担となります。
有益費については、民法196条によるので、配偶者支払の場合、有益費の価格の増加が現存する場合に限り、償還させることができることになります。
配偶者居住権と転貸
配偶者が建物所有者の承諾を得て、第三者に使用・収益させている場合には、賃貸借契約における適法な転貸規定の民法613条が準用されます。
これにより、第三者は、居住建物の所有者に対し、配偶者と第三者との契約に基づく債務を直接履行する義務を負います。
建物返還義務や損害賠償義務を負うことになるでしょう。
上記の経緯で、第三者に居住建物を使用・収益させた場合、所有者が配偶者との間で配偶者居住権を合意により消滅させても、第三者には対抗できません。
例外として、合意消滅時に、建物所有者が、配偶者の用法遵守違反や無断増改築等の債務不履行があり、配偶者居住権を消滅させることができたときには、合意消滅を第三者に対抗できるとしています。
第三者と所有者の保護のバランスをとっている規定です。
配偶者居住権の消滅
このような強い権利である配偶者居住権がいつ消滅するのかというと、次の場合です。
・期間満了
配偶者居住権の期聞を定めた場合には、期間満了で消滅します。
・配偶者の用法遵守義務等違反
配偶者が、用法遵守義務に違反したり、無断増改築、無断で第三者に使用収益させるなどした場合、建物所有者は相当の期間を定めて、それをやめるよう催告します。それにもかかわらず、期間内に是正されないときは、配偶者に対する意思表示で配偶者居住権を消滅させられます。
・居住建物の全部滅失等
居住建物の全部が滅失等の事由で使用収益できなくなった場合にも、配偶者居住権は終了します。
・配偶者の死亡
配偶者が死亡したときは、期間満了前でも消滅します。
配偶者居住権が消滅したら、当然ながら、建物の返還が必要になります。
配偶者に共有持分があるようなケースでは、配偶者居住権が消滅しても、それを理由に建物の返還を求めることができないとされていますが、それ以外の場合には、返還が必要です。
配偶者居住権消滅後の義務
配偶者居住権が消滅した場合、配偶者は賃貸借契約の終了と同じように義務を負います。
配偶者が死亡した場合には、相続人がこれらの義務を負います。
・原状回復義務
配偶者は、相続開始後に居住建物に生じた損傷を原状に復する義務を負います。
ただし、通常損耗や経年変化は除き、損傷が配偶者の責任でない場合も義務を負いません。
・附属物の収去義務
相続開始後に居住建物に附属させた物を収去しなければなりません。
ただし、建物から分離できない物だったり、分離するのに過分の費用が必要な場合は、この義務を負いません。
相続のご相談は以下のボタンよりお申し込みください。