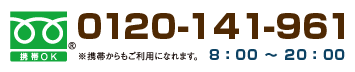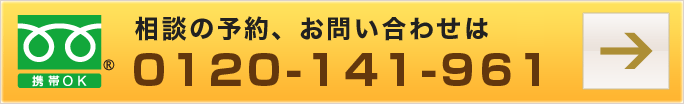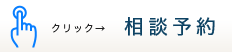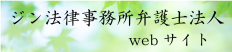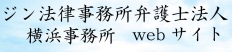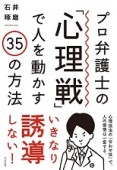よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.認知症の相続人がいる場合は?
遺産分割協議では、相続人全員の署名押印が必要です。
実印の押印と印鑑証明書の添付は必須です。
また、遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要です。
この点、相続人のなかに認知症で意思疎通ができない相続人がいる場合、遺産分割協議を成立させられない可能性が高いです。
遺産分割協議をする法的能力がないと判断されてしまうからです。
2025年には、高齢者の5人に1人が認知症を発症するとも言われており、相続手続きの中では重大な問題です。
成年後見人の選任
認知症等で、判断能力がない相続人には、家庭裁判所へ申立をして成年後見人をつける方法があります。
成年後見人が代理人となり、本人に代わって遺産分割協議に参加します。
この場合、成年後見人の印鑑証明書で対応できます。
成年後見人は、家庭裁判所の監督下にあり、認知症の相続人の利益を第一に優先しますので、その相続人の取り分を減らすような遺産分割協議には応じられないのが通常です。
話し合いが難しい場合には、成年後見人も参加しながら、遺産分割調停や審判になることも少なくありません。
任意後見
すでに認知症が進行し、判断能力がないような場合には、成年後見制度の利用になります。
成年後見制度では、誰が後見人にあるかは家庭裁判所が決めます。
これに対して、現時点で判断能力があるものの、後日の認知症に備えるため、あらかじめ後見人になる人を自分で決めておけるのが任意後見制度です。
子供を後見人として指定することもできます。
後見監督人の監督を受けることにはなりますが、第三者が成年後見人になるよりは、自分の希望どおりの動きをしてもらいやすくはなるでしょう。
この任意後見契約は、公証役場で契約書を作ってもらいます。
このような任意後見制度を利用しておけば、自分が認知症になり、なんらかの相続が必要な場合でも、後見人による遺産分割協議がスムーズに進められます。
認知症を含む相続のご相談は以下のボタンよりお申し込みください。