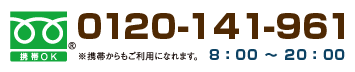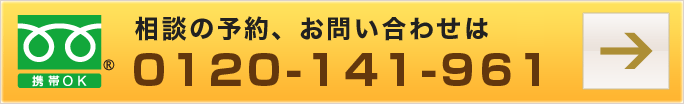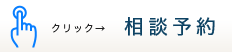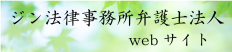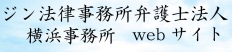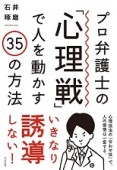よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.預貯金の相続手続きは?
亡くなった方の預貯金の相続手続は、銀行や信用金庫など金融機関ごとに決められた相続手続を行わないといけません。
自宅から出てきた資料などで預貯金口座の存在が確認できたら、まずは相続発生の事実を各金融機関に伝えます。
これにより口座は凍結されます。入出金はできなくなります。
口座振替も止まります。
光熱費等の支払を口座振替でしていた場合には、名義変更や振替口座の変更をします。
金融機関への連絡の際、相続に必要な書類についても、ある程度確認するとよいでしょう。
また、窓口であれば、残高証明の請求をすることも考えられます。
残高証明の請求は、相続人の1人だけでも行うことができるとされています。
預金の相続手続き
預貯金の相続手続では、各金融機関で決められた届出用紙の提出を求められます。
銀行、金融機関ごとに違う用紙なので、それぞれ入手する必要があります。
窓口や郵送で届出用紙や必要書類を受け取り、戸籍謄本類などの必要書類はまとめて入手するとスムーズです。
戸籍謄本等や印鑑証明書などの書類は、原本還付がされるかを確認し、必要な通数を集めます。
各相続人に印鑑証明書をもらうとともに、相続届などの必要書類へ署名・捺印をしてもらいます。
書類が揃ったら、金融機関に提出し、払い戻しを受けられます。
金融機関によっては、提出後、数週間の期間がかかることもあります。
多くの金融機関の窓口では受付だけし、その後、相続センター等の担当部署で審査します。窓口ですぐに、お金が引き出せるわけではありません。
通常、相続に関する書類の提出は、預金口座のあった支店で対応してもらいますが、遠方などの事情がある場合には、近くの支店で対応できないか確認してみると良いでしょう。対応してもらえるか、金融機関によって違います。
また、地方銀行などで近くに支店すらない場合は、地元にいる相続人がいれば、その人を代表者として手続きをしてもらい、他の相続人に分配できるとスムーズに進められます。
ゆうちょ銀行のセンター
ゆうちょ銀行の貯金などの相続手続も、基本的には銀行等と同じ流れです。
ただ、相続に関しては、貯金事務センターで取り扱いをすることになります。
まず、最寄りの郵便局で相続が発生した旨を伝えて、相続確認表をもらいます。
相続確認表に必要事項を記入し、郵便局の貯金窓口に提出。
この書類が、貯金事務センターに回されます。
その後、貯金事務センターから、必要書類の案内が、送られてきます。
そこから準備することになります。
案内に書かれた、必要書類一覧を確認しましょう。
他の銀行等と同じく、戸籍謄本や印鑑証明書などが必要になります。
また、各相続人が署名押印した相続手続請求書も必要になります。
これらを、当初手続した、郵便局に提出します。
被相続人名義の貯金を払い戻すか、名義書換とするかによって手続は変わります。
払戻しの場合は払戻証書、名義書換の場合は名義書換がされた通帳が、貯金事務センターから届きます。
払戻証書であれば、郵便局に行き、払戻手続をします。
手続にかかる時間と代理人
銀行等の金融機関の窓口では、手続に待たされる時間も長いことが多いです。
相続手続の際は、1~2時間待たされることもあります。
あらかじめ電話などで必要書類等を確認してから行くことで時間が短縮されることもありますが、覚悟はしておきましょう。
そのような手続が負担だとして、相続人以外の人が相続人に代わって相続に関する手続を行う場合、委任状など所定の書類を各金融機関に提出する必要があります。
この委任状も金融機関によって変わります。
委任事項の書き方も金融機関によって変わることもあり、この委任状の取り寄せにも時間がかかってしまうのが実情です。
遺産分割がまとまらない場合の出金は?
平成28年最高裁決定により、当然分割は否定され、預貯金も遺産分割の対象となっています。
相続財産となった預貯金を払戻すよう請求できるのは、相続人全員の合意、遺言がある場合、遺産分割審判などに限
られます。
預貯金の仮払い制度は?
預金について、遺産分割等がないと、原則として出金できないものの、例外として、2019年7月施行の改正法では、仮払い制度が認められています。
当面の生活費や葬儀費用のための資金等として、各相続人は、相続財産の預貯金のうち相続開始時の3分の1に法定相続分を乗じた額について、単独で払い戻すことができるとされました(改正民909の2、民法第909条の2に規定す
る法務省令で定める額を定める省令)。
他の共同相続人の同意がなくても払戻を受けられます。
ただし、上限が150万円とされています。
この上限については、金融機関ごとに判断するとされています。同一の銀行の場合、支店が違っても同じ銀行からは150万円が上限です。
たとえば、法定相続分が2分の1(例:配偶者と子)という場合で、ある銀行預金の残高が600万円というケース。
この場合、600万円✕3分の1✕2分の1で100万円の払戻を受けられる計算です。
この払戻請求をする場合には、相続の証明のため、戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写しの提出が必要です。
また、金融機関では、遺産分割協議が未了であることや遺言等がされていないことの確認がされます。
相続人が仮払いによる払戻しを受けた場合には、遺産分割において、この相続人が一部分割により既に取得したものとみなされます。
この払戻請求権については、第三者に譲渡したり差し押さえをすることはできないとされます。
遺言による預金からの出金は?
遺言特定ので、相続人に預貯金を相続させる旨の記載がある場合、原則として、その相続人だけで相続預貯金の払戻請求を行うことができます。
このように、預貯金を相続させる旨の記載がある遺言の解釈として、特段の事情がない限り、遺産分割の方法を定めたものとされ、被相続人死亡時に、何らの行為を要せずして、直ちに当該預貯金は当該相続人に相続により承継されます(最判平成3年4月19日)。
この権利の取得に関して、対抗要件がなくとも第三者に対抗できるとされていました(最判平成14年6月10日)。
この点について、2019年改正相続法では、相続による承継も、法定相続分を超える部分については、対抗要件の具備が必要とされています。
債権の権利承継については、受益相続人が遺言の内容を明らかにして債務者に通知することで、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなす旨の規定があります。
これらの規定により、相続法改正前後を問わず、遺言による相続預貯金の払戻請求については、原則として受益相続人だけで払戻請求できると考えられます。
その際には、公正証書遺言の場合には、公正証書遺言の正本又は謄本の提出、自筆証書遺言の場合には、検認済証明書等も必要です。
公正証書遺言は、原本が作成した公証役場で保管され、正本と謄本が交付されています。謄本は、原本の内容を記載した写しのことです。正本は、謄本の一種で、原本と同じ効力のものです。
なお、相続法改正により、遺言執行者の預貯金の払戻し権限が明確化されています。
遺言執行者は、預貯金債権について、払戻請求や解約の申入れをできると明記されています(改正民1014条)。
解約の申入れができるのは、預貯金債権の全部を特定の相続人に承継させる旨の遺言の場合です。
遺言の預金指定が間違っている場合は?
遺言で、預貯金の相続について書かれているものの、内容について誤記があることもあります。
例えば、銀行の名称を間違えたりしている場合です。
このような誤記があると金融機関に対して払戻請求をしても、預貯金の特定が不十分だとして、払戻ができないことが多いでしょう。
相続人全員により払戻請求を行うか、相続人全員を被告にして、遺言の解釈として相続預貯金が受益相続人に帰属していることの確認請求訴訟をする方法が考えられます。
貸金庫の契約
銀行の預金口座以外に、貸金庫の契約がされていることもあります。
貸金庫契約の法的性質については、最高裁平成11年11月29日判決が「貸金庫の場所(空間)の賃貸借である」としています。契約者たる被相続人が死亡した場合、貸金庫契約上の地位は、被相続人の相続人に承継されるとしています。
遺言書で、被相続人死亡の際の貸金庫開扉の権限が遺言執行者、あるいは預貯金受遣者など明示的に与えられている場合、それに従うことになります。
判例の中には、遺産分割協議書で「その余の財産全部」を取得するとされた者に貸金庫使用権の帰属が認められるとしたものがあります。貸金庫使用権があることの確認訴訟の事件です。
実務では、相続人全員による貸金庫開扉請求に銀行は応じています、一部相続人からの開扉請求には応じていないことがほとんどです。
ただし、公証人により「事実実験公正証書」を作成するとして、貸金庫の内容点検を行う方法であれば、一部相続人からの請求でも応じることが多いです。
公証人は、直接体験(事実実験)した事実に基づいて公正証書を作成することができるとされています。事実実験の結果を記載した「事実実験公正証書」は、証拠保全としての機能を有するとも評価されています。
ジン法律事務所弁護士法人でも、相続に関する手続のご相談も受けておりますので、ご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みください。