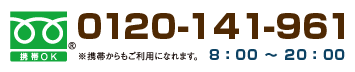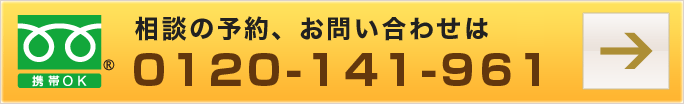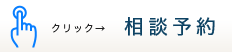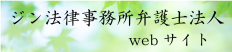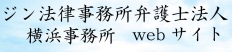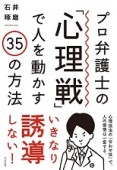よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.相続財産の調査は?
相続手続では、どのような相続財産があるか調べなければなりません。
できる限り調べ、全体像を把握してから分割の話し合いをすべきです。
全体像を把握しなければ手続を間違えてしまうこともあります。
居住物件での調査
まずは、被相続人が住んでいた自宅などの居住物件内で資料を探しましょう。
自宅の金庫やタンス、棚など、大事なものを保管している場所を探しましょう。
預金通帳や鍵の保管状態から、貸金庫の契約をしている形跡があれば、貸金庫内に相続財産に関する書類が保管されている可能性が高いです。
貸金庫を契約者や指定代理人以外の人が開けるためには、通常は、戸籍謄本等、相続人であることを示す資料が必要です。
自宅で探す資料としては、通帳、カード、金融機関の証券類(出資証券)、株券、金融機関、仮想通貨業者等からの郵便物(有価証券)、不動産に関しては権利証、登記簿謄本、売買契約書、固定資産税に関する資料、債務について借用書や請求書があります。
また、通帳や口座取引明細から他の預金や証券会社、借金が判明することもありますので、可能な限りさかのぼって確認しましょう。
通l帳に記載された引き落としや入金、振込などの取引明細を細かくチェックするのです。
金融機関や証券会社に取引がある場合や生命保険などは、定期的に郵便物が届くことが多いです。
これらもチェックしましょう。
銀行の情報などがわかったものの、内容が不明の場合には、金融機関に問い合わせて開示してもらいます。
相続不動産の調査
不動産については、自宅から権利証や固定資産税に関する資料が見つかった場合には、その情報から、法務局で登記事項証明書を取得したり、役所で名寄帳などを閲覧します。
不動産の地番や家屋番号を調べて、法務局で不動産の登記事項証明書を取得すれば、その不動産の権利関係が確認できます。今の所有者が誰なのか、抵当権が設定されているのか、債務が残っているのか等が確認できます。
また、名寄帳を閲覧すると、同一市区町村内にある被相続人所有の不動産をすべて確認することができるはずです。
複数の不動産を持っていた可能性がある場合、漏れがないかどうか確認できるので、念のため調査しておきましょう。
不動産の登記事項証明書は、コンピュータ化、ネットワーク化されているため、近くの法務局で全国の不動産の情報は確認できます。また、登録をすれば、インターネットでも内容の確認や謄本の申請はできます。
登記事項証明書の情報は公開されていますので、誰でも閲覧できます。
なお、固定資産税の納税義務者と登記上の所有者とは必ずしも一致していません。固定資産税については市町村が管轄であり、登記の名義は法務局が管轄となっています。
なかには、固定資産税を自分が払っているから登記名義も変わっているだろうと考えていたら、相続の対象となり未分割の遺産であったということもありますので、ご注意ください。
名寄帳の閲覧は、市区町村役場や都税事務所でできます。
所有者のほか相続人もできますが、名義人との関係を証する資料や身分証明書が必要になります。
手数料は、役所によって異なります。