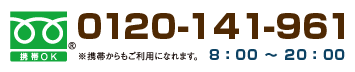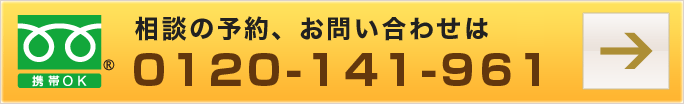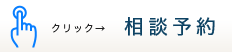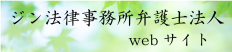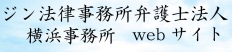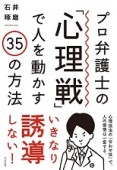よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.戸籍謄本の取得はどうすれば良い?
相続財産の名義変更など相続の手続や届出の際には、相続人であることを示す戸籍謄本等の提出を求められます。
相続人であることの照明は、役所が発行する戸籍謄本関係で、金融機関や法務局は確認します。
まず、亡くなった被相続人の戸籍には死亡の記載がされます。この戸籍謄本や除籍謄本だけでは、その人が死亡したことしかわからず、相続人が誰かを証明するには不十分です。
また、戸籍は転籍や法改正、コンピュータ化などによって、新しくつくられていることもあります。
古い戸籍にあった抹消情報は、基本的に新しい戸籍に記載されません。古い戸籍は、改製原戸籍と呼んだりします。
そのため、新しい戸籍の内容だけでは、相続人全員の確認ができないのです。
そのため、相続関係を証明するためには、亡くなった被相続人の全ての戸籍をさかのぼる必要があります。
手元に資料がなければ、一つずつ順番に取得しなければなりません。
亡くなった被相続人の戸籍をさかのぼって取得すると、過去の婚姻関係や親子関係が記載されています。
このように昔の戸籍を確認し他に相続人がいないことを示します。
兄弟姉妹が相続人となるときは、両親の昔の戸籍も取得し、他に兄弟姉妹がいない(=両親には他に子がいない
こと)を示す必要があるのです。
相続人の発覚?
戸籍をさかのぼって確認したら、予想外の相続人が見つかることもあります。
過去に離婚歴があり、子がいることが判明したり、婚外子がいることが判明したり、認知していたり、養子縁組をしていたりすることもあります。
このような相続関係が発覚したとき、無効だと主張したくなる気持ちは分かるのですが、なかなか無効だと確認されることは難しかったりします。
親子関係などが無効にならない限り、発覚した相続人も含めなければ相続手続きは進められません。
そのような相続人には、通常、戸籍の附票から住所を確認できるので、そちらに通知したり、会いに行くなどして、相続のことを伝え、交渉することになります。
連絡が取れない相続人は?
戸籍で相続人を把握する際、その相続人と面識があるのか、連絡が取れるのかもチェックしておく必要があります。
長年、音信不通だったり、認知症が進んでしまっている相続人がいることもあります。
住所すらわからない場合には、戸籍の附票で住所確認する必要もあります。
相続人が確定しても連絡が取れない場合には他の手続きをしなければならないこともあります。
戸籍謄本等の取得方法
戸籍謄本は、公開されているものではありません。
誰でも取得できるものではありません。
配偶者、親などの直系尊属、子などの直系卑属のように、法律で請求できる人は決められています。
これが取得できるのは、戸籍謄本に書かれている本籍地の市区町村役場です。
ここに請求します。
その際、本人確認書類(免許証等)を提示します。
代理して請求する場合には、委任状も必要です。
遠方の市区町村役場の場合には、郵送での申請もできます。
この場合、窓口で支払うはずの手数料は定額小為替で支払ったり、現金書留で送ります。
定額小為替は、郵便局等で購入できます。
なお、戸籍謄本とは、戸籍に入っている全員分の写しであるのに対し、戸籍抄本は、一部の人の写しですので、必要な書類を間違えないようにしましょう。
このような戸籍をさかのぼっての相続人の確定が、ご自身では大変だという場合には、法律事務所でも対応できますので、遠慮なくご相談ください。