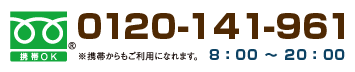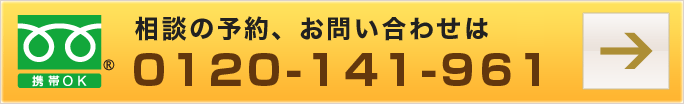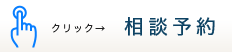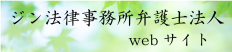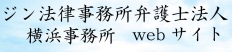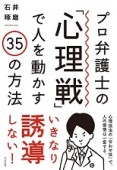よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.死亡後の年金の手続は?
家族の死亡時に、年金関係でやらなければならない手続は2種類あります。
1つ目は、亡くなった方人の年金について、受給停止や未支給の年金を受給する手続です。
亡くなった人自身の年金の対応です。
2つ目は、遺族が受給できる年金や一時金を請求する手続です。
こちらは、ご家族自身の年金の対応です。
たとえば、 遺族が受給できる年金として、遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金)の2種類があります。亡くなった家族が加入していた年金の種類や保険料納付期間によって、もらえる金額は違います。
ご家族にも要件がありますので、それを満たすかどうかチェックしていく必要があります
年金受給の停止
年金受給者が死亡した場合、年金受給を停止する手続をしなければなりません。
年金受給権者死亡届の提出などがが必要です。
手続が遅れてしまい、死後にも年金が振り込まれてしまった場合、返還しなければなりません。
年金は、死亡した月の分まで受け取る権利があります。
まだ振り込まれていない未支給年金は請求すれば、遺族に支払われます。
通常は、年金受給権者死亡届の提出と未支給年金請求を一緒に行います。
未支給分の年金は、遺族の中でももらえる優先度の順位が決められています。
亡くなった方と生計を同じくしていた①配偶者
→②子
→③父母
→④孫
→⑤祖父母
→⑥兄弟姉妹
のように、順位が決められています。
未支給年金を請求する場合には、同時に、亡くなった方の職歴、旧姓などの情報を伝えて、他に未支給の年金漏れがないかを確認します。
遺族年金の申請
次に、自分の年金として遺族年金の請求ができないかをチェックします。
亡くなった方が加入・受給していた年金によって、自分が遺族年金を受けとれる遺族になるのか等を確認します。
遺族年金の制度は、扶養してくれていた一家の支柱が亡くなったことで、家族が生活できない事態をさけるためにあります。
そのため、遺族年金をもらえる人は、亡くなった方に生計を維持されていたことが前提です。
生計維持要件があります。
「生計を維持されていた」とは、亡くなった方と生計を同一にしていた方です。
さらに、年収850万円を将来にわたって得られない方です。
年収要件については、死亡当時の年収だけを見るのではなく、おおむね5年以内に年収が850万円未満になると認められるかどうかが基準となります。
このような要件を満たす人については、遺族年金がもらえる可能性がありますので、調査のうえ、申請を検討しましょう。
労災の年金
会社員等は、労働者災害補償保険(労災)に加入していて、会社が保険料を支払っています。
この労災は仕事中の死亡事故でも補償があります。
遺族補償年金という制度です。
労働者の死亡当時、その収入で生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、および兄弟姉妹が対象になります。
細かい支給の要件があり、誰も支給要件に当てはまらなかった場合でも、遺族補償一時金が支給されることがあります。
労災の事故では、会社が動いてくれることが多いですが、会社によっては労災の申請に非協力的ということもあります。そのような場合には、会社の管轄地にある労働基準監督署に相談してみましょう。