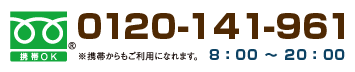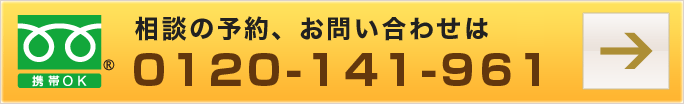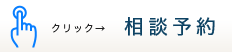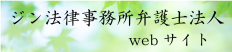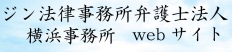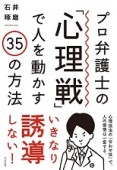よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.家族が亡くなった場合の最初の手続はどのようなもの?
ご家族が亡くなった場合、まず葬儀の話が出てくると思います。
それと並行して死亡届の提出などが必要になってくるでしょう。
葬儀の一般的なスケジュールは、
・親族への連絡
・遺体搬送(葬儀業者と調整)
・葬儀業者等との打ち合わせ、関係者へ連絡、お寺の手配
・通夜
・葬儀・告別式
・出棺、火葬
・納骨
あたりです。
病院からの安置先を決めた後、葬儀業者が遺体の引き取りに来てくれます。遺族も、遺体と一緒に安置先に向かいます。
葬儀業者との打ち合わせでは、形式や規模のほか、祭壇、献花、香典返しのような細かいことも決めます。
具体的なスケジュールを、お寺の住職や家族と調整しつつ、通夜・葬式の日程を決めていきます。職場への休暇連絡などもすることになるでしょう。
死亡診断書・死亡届、火葬許可
これと並行して、役所に死亡届を提出する必要があります。
そのためには、死亡診断書・死体検案書の手配が必要です。
家族が病院で亡くなったときには、立ち会った医師に死亡診断書を発行してもらいます。病気以外の理由で亡くなったときは、死体検案害を交付してもらいます。
事故などの場合、警察経由で監察医から死体検案害を発行してもらうことになります。
これらの書類は、生命保険の申請等に使うこともあるので、コピーをとっておきましょう。
死亡診断書または死体検案書を入手後、死亡地や本籍地、届けをする人の所在地の市区町村役場に死亡届を提出します。
提出は死亡事実を知ってから7日以内、提出をするのは、親族、同居者、家主、後見人などです。
この際、同時に、火葬許可申請書を提出するのが通常です。
火葬後、火葬場から埋葬許可証が出されます。
葬儀業者によっては、このあたりの手続を遺族の使者として対応してくれます。
その後、納骨の準備となります。
お墓ががあれば、そこと相談。ない場合には、購入の検討をします。
そもそも、お墓を管理できない場合などは、お寺が供養と管理をする永代供養にするという選択肢もあります。
このような流れが一般的と言われますが、最近は、通夜、葬儀などをせずに火葬のみする直葬も増えているそうです。
葬儀業者は、病院の担当者から「葬儀業者は決まっていますか?」と紹介してもらえることもありますが、検討時間がないことがほとんどです。生前に探せるようであれば、検討しておいた方が無難ではあります。