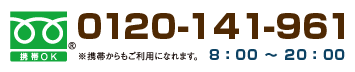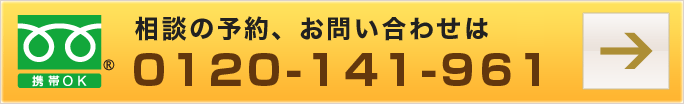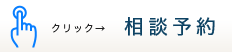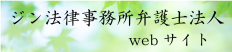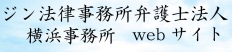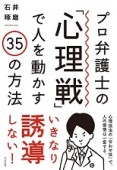ケース紹介・解決事例
解決事例
お墓に関する紛争事例
東京都内にお住まいの60代女性からのお墓に関する相談でした。
親族に、ご先祖様のお墓を無断で移動させられたという相談でした。
このような紛争だと祭祀承継者の問題が出てきます。
祭祀承継者とは
祭祀承継者とは、祭祀財産や遺骨を管理し、祖先の祭祀を主宰する人。
民法では、897条1項で次のとおり書かれています。
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」
系譜、祭具及び墳墓が祭祀財産となります。
系譜は、祖先からの系統、家計を表示するもの。
祭具とは、位牌、仏壇等の祖先の祭祀、礼拝の用に供されるもの。
墳墓が、墓石・墓碑などの墓標や埋棺を示します。裁判例では、墓地も祭祀財産になるとされています。墳墓と社会通念上一体の物としてよい程度に密接不可分の関係にある範囲の墳墓の敷地である墓地は祭祀財産に属するとされています。
そうすると、お墓を勝手に動かされたことで何らかの請求をできる人とは、祭祀承継者ということになります。
祭祀承継者はどうやって決まる?
上記民法817条1項では、慣習と書かれていますが、この条文には続きがあります。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。べき人のことです。
つまり、決め方の順位としては、まず被相続人の指定が第1順位、第2順位が慣習、第3順位が家庭裁判所ということになります。
実際に家庭裁判所で祭祀承継者の指定を争う事件もあります。
被相続人の指定は、遺言書がある場合には、この条項を含めることも多いです。これは明確な証拠になります。書面による指定に限定されておらず、口頭でも良いですし、黙示でも良いとされます。裁判例では、財産をすべて一人の子に贈与したことから、祭祀承継者も指定する意思だったとした事案があります。
慣習を主張することもあるのですが、紛争になった場合には立証が難しく、結局、家庭裁判所に持ち込まれる流れになることが多いです。
家庭裁判所では、乙類審判事項とされ、調停または審判で決められます。
審判例で決められる基準としては、被相続人との身分関係、過去の生活関係、承継者の意思、能力、他の利害関係人の意向などを総合的に判断するとされています。
祭祀承継者を合意で決められる?
法律では、上記のとおり、祭祀承継者の決め方が3通り規定されています。
しかし、指定がなく、慣習もない場合に、裁判所ではなく、相続人間で決めることができないかという視点もあります。事実上、このような決め方がされているご家族も多いといえるでしょう。
遺言書がない相続事件も多く、明確な慣習がないことがほとんどです。
それにもかかわらず、家庭裁判所で、祭祀承継者の指定事件はそれほど多くありません。
実際には、相続人の間で話し合って、お寺との関係で代表者を決めるみたいな感じで決められることが多いといえます。
法的には、条文を解釈すれば、このような決め方は認められておらず、許されないという考え方もありますし、審判例もあります。しかし、調停で決められることからすれば、あえて否定する必要もなく、合意で決めることが許されるとした裁判例もあります。
関係者が合意している以上、後日、紛争になることはそこまで多くないというが実情でしょう。
祭祀承継者は1人?
次に、祭祀承継者の人数が問題になりそうです。
自分がお墓を管理している祭祀承継者だと主張しても、相手が自分も祭祀承継者でお墓を移動できると主張したら、双方に権限があることになってしまいそうです。
祭祀承継者については、祭祀財産を相続財産から外し、共同相続の対象から外していることからすれば、1名にすべきだという裁判例もあります。
しかし、特別事情があれば、分割承継や共同承継を認めて良いともされています。系譜・祭具の承継と、墳墓の承継を分けた裁判例もあります。
なお、祭祀承継者には資格は必要なく、相続人でなくても良いとされています。
遺骨をめぐる紛争
お墓と絡んで遺骨をめぐる紛争というのもあります。
過去に動画で解説したことがありますが、祭祀承継者も問題になっています。
遺骨に関しては分骨請求などがされることもあります。
お墓の移動に関する交渉
上記のような知識を前提として、本件では、お墓を移動した親族に対して、通知を送りました。
依頼者が、代々の祭祀を承継し、祭祀承継者であることを主張。
墳墓及び墓石の権利が依頼者に帰属していると主張しました。
それにもかかわらず、承諾なく墓石を廃棄し、移動したことは、権利侵害だと主張したものです。
最初の通知では、墳墓を原状に復することを請求し、遺骨の所在についても報告を求めました。
その結果、相手方にも弁護士が代理人としてつき、謝罪文の提示がされるなど交渉が進展しました。
最終的には、お墓の移転経緯の事実確認や引き渡し、慰謝料の支払を認める合意書を作成し、和解による解決ができました。
お墓に関する法律相談をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みください。